 私
私私は小2と年中の2児の母です。上の子の発達障害もあり、ワンオペ育児中のテレビつけっぱなしが気になる…
ワンオペ育児中、テレビは子どもが夢中になってくれる欠かせないアイテムですよね。
「どれくらい見せていいの?」「子どもの視力や発達への影響は?」と心配しながら「でも、テレビに頼らないと家事が回らない…」と悩むママも多いのではないでしょうか。
調べてみると、ワンオペ育児でテレビに頼ることは悪いことではなく、テレビとのつきあい方が重要ということが分かりました。
- ワンオペ育児でテレビがつけっぱなしになる理由と心配
- テレビのつけっぱなしが子どもに与える影響
- 専門家の見解やテレビとのつきあい方
テレビを上手に活用することで、ママの負担を減らしながら子どもの成長発達もサポートできるでしょう。
一人で頑張っているママが、少しでも心軽やかに育児を楽しめるよう、ぜひ参考にしてください。
\液晶を保護してブルーライトもカット!/
ワンオペ育児でテレビつけっぱなしの理由


アカチャンホンポの553人を対象とした調査では、回答者の95%が「テレビやYouTubeなどの映像を子どもに見せている」という結果になっています。
子どもに映像を見せる場面トップ5は「家事をするとき」「ぐずったとき」「見せたいものがあるとき」「遊びのレパートリーが尽きたとき」「休憩したいとき」です。
「見せたいものがあるとき」以外の場面では、他に子守りを頼める大人がいないという潜在的な理由が伺えます。



ワンオペ育児をしている多くのママが、テレビに頼りながら子育てをしていることが分かりますね。
ワンオペ育児でテレビがつけっぱなしになる理由と、ママの心の声を詳しく紹介していきます。
テレビを見せる場面TOP5


テレビを見せる場面TOP5「家事をするとき」「ぐずったとき」「見せたいものがあるとき」「遊びのレパートリーが尽きたとき」「休憩したいとき」の背景にはどんな理由があるのでしょうか。
| 子どもにテレビを見せる場面TOP5 | 理由やママの思い |
|---|---|
| 1位 家事をするとき | 家事を中断せずに終わらせたいから、子どもにはご機嫌でいてほしい 家事で子どもから目を離す間、テレビに集中していてくれると安全面でも安心 おんぶで家事は体力的にきつい |
| 2位 ぐずったとき | 本泣きや癇癪になると計画通りに物事が進まない ぐずり始めに見せて機嫌をよくしたい 本泣きやかんしゃくは母のメンタルも削られるから、できるだけ機嫌よく過ごしていてほしい |
| 3位 見せたいものがあるとき | 子どもに好きな番組があり、見たがっている 知育やダンスなど、親子で楽しみたい |
| 4位 遊びのレパートリーが尽きたとき | いろんな遊びをしてもすぐ飽きたり、拒否されたりするよりは、大好きなテレビは部屋も汚れず手軽 猛暑や病み上がりで外で遊べないけど、家の中の遊びにも手をかけられない |
| 5位 休憩したいとき | テレビを機嫌よく見ていてくれる間に、少しでも座ってひと息つきたい |
ワンオペ育児ではママの負担やストレス最小限で、生活をスムーズに回したいですよね。



家事をサボって子どもといろいろ遊びたいけど、その後始末をするのも自分。結局、テレビに頼っちゃいます…
テレビのつけっぱなしは、TOP5以外にも以下の理由が考えられます。
- 忙しくて、テレビを消し忘れる
- 静かな環境が寂しくBGM代わりにつけている
- ママ自身もテレビのつけっぱなしが日常の環境で育った
子育ての助けとしてテレビを活用している場合もあれば、以前からの生活の延長で何となくテレビをつけっぱなしにしている場合もありますね。
\合わせて読みたい/


多くのママが感じている心配や罪悪感



気がついたら、テレビに近づいてみているときもあって、視力への影響が心配…
アカチャンホンポの調査では、映像を見せるときの心配として以下の項目が上位になっています。
- 第1位 「視力が悪くなるかもしれない」
- 第2位 「親とのコミュニケーション不足」
- 第3位 「夜の寝つきが悪くなるかもしれない」
その他には「覚えてほしくない言葉を覚えるかも」「発語が遅くなるかも」という心配も紹介され、テレビを見せているママの多くが、心配や罪悪感を感じていることが伺えます。
ママの感じている心配や罪悪感は本当なのでしょうか?専門家の意見も見てみましょう!
子どものテレビ視聴についての専門家の見解は?
NHKのすくすく子育てでもおなじみの恵泉女学園大学学長の大日向雅美(おおひなた まさみ)先生の見解をご紹介します。



いつもママに優しい言葉をかけてくださる大日向先生が大好きです!


- テレビを見せることに罪悪感は必要はないが、見せ方を選ぶことは大切
- 見せる内容を選ぶ
- 見せる時間を意識する
- 親と一緒に見る時間も作る
- だらだらと長時間見せない
- 絶対ダメではなく、生活に応じた柔軟なルール作りを
大日向先生はさまざまな番組やコラムで以下のように訴えていらっしゃいます。
ワンオペ育児でテレビをつけっぱなしにしてしまうのは、決して怠けているわけではなく、限られた環境の中でママが最善を尽くしている証拠と言えますね。
テレビをはじめとする映像の視聴が子どもに与える影響について、より詳しく見ていきましょう!
ワンオペ育児でのテレビの影響と対策


環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査」などの研究から、テレビの長時間視聴は発達全般の遅れや視力低下につながることが分かっています。



耳が痛い研究結果…でも、悪影響への不安なくワンオペ育児にテレビを有効活用したい!
ルール作りやワンオペ育児の不安軽減のためにも、テレビが子どもの視力や発達、寝つきに与える影響について、正しい情報を知っておきましょう!
視力の低下
視力が完成する3歳になるまでは、2時間以上のテレビの視聴と、画面からの近さが視力低下につながることがわかっています。


- 1歳半、2歳半でテレビ視聴時間が長い子どもは、その後小学生になったときに「視力が悪くなった」と感じる親の割合が多い
- 特に2歳半時点で1日2時間以上テレビを見る子どもは、1時間未満の子どもと比べて小学生時の視力低下リスクが高い傾向
- 3歳以降のテレビ視聴時間と小学生時の視力低下には明らかな関連は見られない
- 以上のことから、視覚が発達する3歳までは、テレビ視聴が2時間以上にならないように注意が必要
参考元 岡山大学
子どもがテレビ画面を見る場合は、画面の高さの3倍を目安に、できればさらに距離をとるのが望ましいとされています。
| テレビのサイズ | 画面高さ | テレビからの距離の目安 |
|---|---|---|
| 32型 | 約39cm | 約1.2m以上 |
| 40型 | 約50cm | 約1.5m以上 |
| 46型 | 約57cm | 約1.7m以上 |
| 52型 | 約65cm | 約1.9m以上 |
| 60型 | 約75cm | 約2.2m以上 |
ご自宅のテレビサイズとあわせて確認してみましょう!



テレビは離れられるけど、子ども自身がスマホやタブレットを持って見るのは近くなりやすいですよね!
小さな子どもは手が短く、距離を保って持つことも難しいので、スタンドやホルダーを活用して適切な距離を保ちたいですね。
\置いて距離を保とう!/
寝つきの悪さや睡眠の質低下
ブルーライト対策グッズが一般的になり、テレビなどの画面から出る光(ブルーライト)が寝つきを悪くすることは、ご存知のママも多いのではないでしょうか?
寝る前にブルーライトを浴びることで脳が刺激を受け、眠気を誘発するホルモン「メラトニン」の分泌を妨げてしまうため、寝つきや睡眠の質に影響してしまうのです。
生活の中で、以下の様子が気になる場合は、寝る前のテレビ視聴時間を確認してみましょう。


- 寝つきが悪い、寝るまでに時間がかかる
- 夜泣きや夜中に目が覚めやすい
- 朝の目覚めが悪い
- 日中の眠そうな様子や集中しにくい様子がある
小さな子どもは大人よりも光の影響を強く受けやすいため、特に寝る前のテレビ視聴は避けるべきとされています。
寝る前の過ごし方も参考にし、親子で睡眠の質を良くしましょう!


- 寝る1~2時間前にはテレビを消し、端末画面も見せない
- 部屋の明かりを暗めにする
- 寝室にテレビやスマホを置かない



わが家は寝る前に家族ですごろくやボードゲームをして過ごすことがあります。
\小さい子から大人まで夢中になれる!わが家のおすすめゲーム♪/
言葉や運動など子どもの発達の遅れ
テレビの長時間視聴で、言葉の発達や運動の発達への影響がみられることが明らかになっています。
日本小児科学会が2003年に実施した大規模研究や、1歳~3歳児57,980人を対象にしたエコチル調査(環境省子どもの健康と環境に関する全国調査)の結果を以下に紹介します。


<日本小児科学会>
- 1日4時間以上テレビを見る子どもは、4時間未満の子どもに比べ言葉の発達が1.3倍遅れる
- テレビが8時間以上ついている家庭の子どもも、言葉の発達の遅れが見られる
- 親の関わりが少ない長時間視聴では、意味のある言葉を話す時期の遅れが大きい


<エコチル調査>
- 1歳、2歳、3歳時点でのテレビ·DVD視聴時間と発達状況を分析
- 視聴時間が長いと、1年後の発達スコアが低くなることを1歳~3歳の全ての年齢で確認
- 1~2歳ではコミュニケーション能力への影響が大きい
- 2~3歳では大きい運動、細かい運動、コミュニケーションへの影響が大きい
- コミュニケーションの発達が高いと翌年の視聴時間が短くなる傾向
参考元 国立成育医療研究センター



影響を見て焦りましたが、「見ないときは消す」を心がければ大幅に減らせそう!
研究の考察では、テレビが8時間以上つけっぱなしになると親子のコミュニケーションや遊びの時間が減少するため、言語や社会性の発達への影響が大きいと考えられています。
エコチル調査からは、コミュニケーションの発達とともに視聴時間を抑えられる傾向も示され、1~2歳の早い段階で長時間視聴を避けることがより大切と言えますね。
テレビを見せることのメリット





最近のEテレは大人でも勉強になる番組がたくさんありますよね!
4時間以上のテレビ視聴で子どもの発達への悪影響が示されていることを紹介しましたが、良い影響が報告されている視聴方法もあります。
白百合女子大学の菅原ますみ(すがわら ますみ)教授の研究では、親が子どもに問いかけをしながら一緒に見る場合、最も理解度や単語の習得に効果がありました。
テレビ視聴には以下のように、2つのパターンがあり、良い影響を与える視聴方法のキーワードは「積極的視聴」と「会話」です。
| つけっぱなし (背景視聴) | 積極的視聴 |
|---|---|
| テレビがついているが、他の活動をしていて見ているわけではない 家族の会話が少ない | 子どもが画面に集中して見ている 親も一緒に見て、歌ったり話しかけたりする 番組内容について会話をする |



ワンオペ育児で一緒に見られないからテレビに頼っちゃうんだけど…
横に一緒に座って見られなくても、わが家では料理や食器洗いをしながら「今の言葉良いね!」「ダンス上手!」など子どもと会話を交わすことがあります。
動画は自動再生で次々に好みの動画が流れてくるため、楽な場面もありますが、ときどき一緒に見ると「こんなストーリーの動画を見ていたのか!」と驚くこともありますよ。
ワンオペ育児でのテレビとのつきあい方


テレビは「推奨時間」や「生活も含めたルール」「番組の選び方」で上手なつきあい方をすることで、ワンオペ育児の強い味方にできます。
ここまでの専門家のアドバイスや実際の体験談から、具体的なつきあい方をご紹介します。
それぞれの家庭事情やワンオペ育児に合ったテレビの活用方法の参考にしてください。
年齢別のテレビ推奨時間
視力や発達の面から「2歳未満の視聴はなるべく控える」「2歳以上では1日2時間以内」がテレビ視聴の推奨時間です。
3歳以降は視機能や理解力が発達し、より楽しみ方の幅が広がるでしょう。
<2歳未満>


- 世界保健機関:画面視聴は推奨しない
- 日本小児科医会:画面視聴はなるべく控えて
- Eテレでは0歳から楽しめる人気番組として「いないいないばあっ!
- 」を放映
- 「いないいないばあっ!」は発達心理の専門家が監修し、リズム、繰り返しなど、赤ちゃんが楽しめる工夫が満載
- 1回15分程度で親子での視聴はおすすめ
<2歳~3歳>


- 世界保健機関:1日1時間以内
- 日本小児科医会:全画面視聴は1日2時間以内、ゲームは1日30分以内に
- 画面との距離を保つことに特に注意(画面の高さ×3以上離れる)
- Eテレや動画のキッズアカウントを活用し、学習効果の高い番組を選ぼう
- 親子での視聴、会話がおすすめ
<3歳以上>


- 2歳と視聴の推奨時間は同じ
- 目の機能が完成し、将来の近視リスクは低下傾向
- 手の機能や、コミュニケーション能力も発達
- 短時間ならスマホを自分で持って見たり、決まりを守って視聴をやめたりできる子どもが増えてくる
- リモコンの操作方法を覚え、自分でテレビをつけて見ることも
わが家は休日は2時間を超えてしまっています。
未就園のお子さんとのワンオペ育児では「2時間は厳しい…」「無理…」と思われた方も多いのではないでしょうか。



1歳未満の兄弟がいたら、下の子に合わせないとダメだよね?
兄弟の年齢にもよりますが、3歳差兄妹のわが家では以下のような工夫をしていました。
- 上の子がテレビを見ているときは下の子をおんぶして家事
- Eテレなど2人そろって楽しめる番組を選ぶ
- 下の子のお昼寝中に見せる
もちろん、完璧ではありませんが、できる範囲の工夫でOK!と割り切り、笑顔で過ごせることも大切ですね。
生活も含めたテレビのルール


テレビをつけっぱなしにしていると、お子さんがやるべきことに集中できない、よくこぼす、よく転ぶといった経験はありませんか?
視聴の合計時間以外にも、けじめある生活にできるよう「食事中は見ない」「やるべきことを済ませてから」など視聴のルールを決めましょう。
- 食事中は見ない
- 身支度や宿題など、やるべきことが終わってから見る
- 寝る1時間前からは見ない
- 見たい番組が終わったらつけっぱなしにしないで消す
- 動画ではキッズアカウントと大人のアカウントを分けるなど、見られる番組を制限する
小さなお子さんの場合は「ルールを決めてもわからない」と思わずに、ルールを実際に行動して見せてあげましょう。
年中~小学生など、大きくなってきたお子さんには、遊びも兼ねたチケット制もおすすめです。
<チケット制のやり方♪>
- 1日分のテレビチケットを朝渡す
- テレビを見る時にチケットを渡してもらう
- チケットがなくなったら一日のテレビ時間は終わり



チケットづくりを子どもにやらせれば、工作の時間も確保できて一石二鳥ですね!
見せる番組の選び方とおすすめ5選!
お子さんにテレビを見せながら、家事などで目を離すことも多いのがワンオペ育児の特徴です。



洗濯物を干して戻ると、よく夫が見ていたゲームの実況動画が自動再生されていました…
子どもの発達を考慮した、成長や学びに良い番組を選ぶことで、ママ1人でも安心して家事や休息ができますので、番組や動画選びの参考にしてください。


<おすすめの番組>
- NHK Eテレの番組
- 歌や手遊び、ダンスなど音楽中心の番組
- 知育要素のあるアニメ
- 自然や動物の番組
<避けたい番組>
- 暴力的なシーンがある
- 性的な内容など大人向け
- 刺激が強い音や映像
- 教育的要素がない
ここからは、おすすめ番組を5つご紹介します。
①おかあさんといっしょ


2歳ごろから楽しめる教育エンターテインメント番組。
歌・体操・人形劇・アニメなど楽しいコーナーがいっぱい!
幼児の情緒や表現、言葉や身体の成長を応援します。
内容によっては、0歳の赤ちゃんからも楽しめるものがありますよ。
<放送時間>(2025年7月現在)
Eテレ 毎週月曜~土曜の午前7時45分、毎週月曜~金曜午後6時
②シナぷしゅ


「赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ~」と抜ける」がコンセプト。
民放初の乳幼児向け番組です。
「赤ちゃんが泣き止む動画」などのYouTube動画コンテンツも豊富でワンオペ育児の強い味方!
<放送時間>(2025年7月現在)
テレビ東京系列6局ネット 毎週 月曜~金曜 あさ 7時~8時
テレビ東京ローカル 隔週 金曜 夕方5時30分~5時55分
③デザインあneo


デザインっておもしろい!デザインって心地いい!
身の回りのデザインにこめられたよりよく生きるための工夫や思考を 斬新な映像と音楽で こどもたちに楽しく伝える番組です。
子どもだけでなく、大人の勉強にもなり、親子での会話がはずみます。
<放送時間>(2025年7月現在)
Eテレ 木曜の午後7時50分~8時(九州沖縄地方をのぞく)
Eテレ 土曜の午後9時50分~10時
Eテレ 水曜の午前8時35分~8時45分
④ピタゴラスイッチ
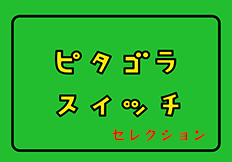
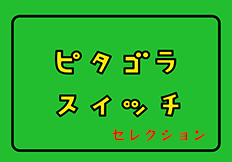
ふだんの何気ない暮らしにかくされた、ふしぎな法則や物事の構造、おもしろい考え方。
そのふしぎを人形劇やピタゴラ装置、歌やアニメなどなるほど!と思えるわかりやすさで伝え、子どもの「考える力」を育む番組です。
幼児には初めての理科や数学的な考え方が楽しみながら学べるのはもちろん、大人も楽しめることに定評があります。
配信動画コンテンツも充実していますよ!
<放送時間>(2025年7月現在)
Eテレ 毎週月~金曜日の午前6時45分~6時55分
Eテレ 毎週月~木曜日の午後6時40分~6時50分
⑤YouTubeチャンネル まじめなえほん
特別支援学校の先生が作った、健康診断の解説アニメ動画です。
就学前の幼児にも分かりやすい解説で、保育園、幼稚園の健康診断や就学時検診前の予行演習におすすめ。
わが家の息子には発達障害があり、見通しが持てないと不安になりますが、健康診断の解説動画を見せて学ぶことで安心して学校の健康診断を受けられました。
公共の交通機関に乗るときのマナーやお友達とのかかわり方など、いろんな解説動画に教えてもらったと言っても過言ではありません。



いろんな動画を作ってくださる方がいて、本当に感謝しています!
番組や動画の内容を確認して、有意義なテレビ、動画とのつきあい方を見つけましょう!
\テレビが見やすいベビーサークルで距離と安全を確保!/
まとめ


- アカチャンホンポの553人を対象とした調査では、回答者の95%が「テレビやYouTubeなどの映像を子どもに見せている」
- テレビを見せる場面TOP5は「家事をするとき」「ぐずったとき」「見せたいものがあるとき」「遊びのレパートリーが尽きたとき」「休憩したいとき」
- テレビを見せる場面TOP5からは、他に子守りを頼める大人がいない状況、ワンオペ育児が伺える
- 多くのママが子どもにテレビを見せることで「視力低下」「コミュニケーション不足」「寝つき」「言葉の発達」への心配を抱いている
- 恵泉女学園大学学長の大日向雅美(おおひなた まさみ)先生の見解は「テレビを見せることに罪悪感は必要はないが、見せ方を選ぶことは大切」
- 環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査」などの研究から、テレビの長時間視聴は発達の遅れや視力低下につながることが分かっている
- 白百合女子大学の菅原ますみ(すがわら ますみ)教授の研究では、親が子どもに問いかけをしながら一緒に見る場合、最も理解度や単語の習得に効果があった
- テレビはつけっぱなしにせず、「視聴時間の管理」や「生活も含めたテレビのルール」「番組の選び方」で上手なつきあい方をしよう
ワンオペ育児でテレビをつけっぱなしにしてしまうことは、決して悪いことではありません。むしろ、消す暇がないほど、頑張っているということです。
「今までつけっぱなしで過ごしてしまった…」というママも、影響を過度に心配せず、テレビとバランス良くつきあうための参考にしてくださいね。
大日向雅美先生も訴えていらっしゃるように、ワンオペ育児は歴史的にもなかったことで、限界です。
テレビ以外の家事や子育ても完璧を求めず、できる範囲で工夫しながら、親子ともに笑顔で過ごせる時間を大切にしていきましょう!










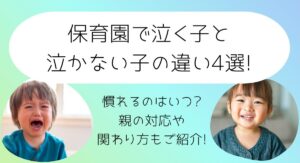


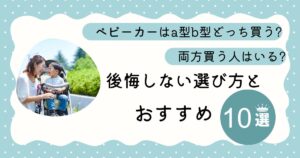
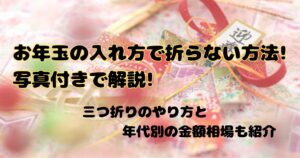
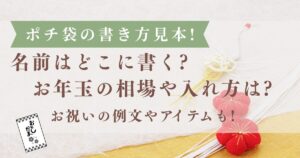

コメント