 私
私私は、3歳の娘と4歳の息子の母です
先日2歳と4歳の子がいる友人から、片づけない子どもに腹が立ち、おもちゃをごみ袋に入れて捨てたふりをしたという話をききました。



こんなひどい親私だけだよね…片づけてほしいだけなのに
私も息子が2歳頃に同じようなことをした経験があります。片づけないからと、捨てたり捨てたふりをすることは効果的なのでしょうか。
調べてみたところ、子どもが片づけない理由から大人がおもちゃを捨ててしまうと、子どもに片づけが身につかないどころか親子の信頼関係を傷つけることにもなりかねないとわかりました。
- 捨てたら自分で片づけるようになるのか?体験談
- こどもがおもちゃを片づけない理由
- 片づける習慣をつける、片付けが好きになるアプローチ
おもちゃをすすんで片づけてくれる子になってほしいと頑張っているあなたも、子どもの気持ちを理解し関わると、心の負担が減って笑顔が増えますよ♪
\頑張っているママにぜひ読んでほしい!収納を見直せば人生もかわる/
おもちゃを片づけないから捨てた!どう育つ?体験談


出しっぱなしのおもちゃにイライラして「片づけないなら捨てるよ!」と言った経験がある、捨てたり捨てたふりをしたことがあるママも多いのではないでしょうか。



おもちゃを捨てたら子どもが自分で片づけるようになるのかな?
捨てたり捨てたふりをした後、子どもが片づけるようになるのか体験談を4つご紹介します。
- 何十回も捨てたが未だに自分で片づけない
- ゲームを隠したが大人になっても片付けができない
- 大事なものなら片づけなきゃと学んだ
- おもちゃを捨てられたことが忘れられない
それでは、詳しく見ていきましょう。
何十回も捨てたが未だに自分で片づけない



娘のおもちゃを今まで何十回も捨てました
3歳頃から、片づけないなら捨てるを繰り返してきましたが、小学生になった今でも片づけを自主的にやることはないそうです。
また、掃除の際「後10分で片づけないなら出ているもの全部捨てるよ」と言うと、捨てられたくないものだけさっさと片付け、「あと捨てといていいよ」と言うとのことです。
“捨てられる”ということがどういうことか理解できる年齢になると、捨てられたくないものは片づけるようになりますが、自分から進んで行動することにはつながっていませんね。
ゲームを隠したが大人になって片づけができない



宿題も片づけもやらずにゲームばかりしていたので捨てたふりをしました
息子さんが中学生の時、宿題も片づけもやらずにゲームばかりするのでゲームを隠したが、大人になった今も一人暮らしの部屋は足の踏み場もないほど散らかっているそうです。
子どもがおもちゃを隠されて学んだことは、【したいゲームができない、だから片づけと宿題をする】です。
自分でやることに結びつないので、大人になっても片づけができないままになってしまいます。
大事なものなら片づけなきゃと学んだ
捨てられた側の意見もご紹介します。



子どもの頃、私がおもちゃを片づけないので母がおもちゃを捨てました
大事なものならきちんと片づけるのは当然、言葉通りの行動をとった両親に今では何の恨みもないそうです。
“今では何の恨みもない”というところがポイントで、当時は悲しさや腹が立つ気持ちもあったそうです。
親子関係が悪化してしまった例をご紹介します。
おもちゃを捨てられたことが忘れられない



子どもの頃、父親におもちゃを捨てられました
子どもの頃に、片づけないという理由でおもちゃを捨てられた20代男性は、大人になった今でも忘れることがなく、親とはそれ以来距離をとっているそうです。
おもちゃを片づけてほしい、大切にしてほしいという子への愛情からおもちゃを捨てたはずなのに、子どもの心と関係に深い傷をつけてしまう可能性があります。
おもちゃを片づけないなら捨てる!与える影響と対処法


前述したとおり、片づけないという理由でおもちゃを捨てると、自ら進んで片づけるようにはなりにくく、場合によっては子どもの心と親子関係に傷をつけてしまいます。
もうすでに捨ててしまった、捨てるふりをしてしまったと後悔しているあなたに、その後の対応次第では影響を抑えたり片づけられるようになったりすることをお伝えしたいのです。
それでは、おもちゃを捨てることが子どもに与える影響からみていきましょう。
子どもに与える影響
おもちゃを片づけない子どもに「捨てる」と言うのは、“おどし”で行動させていることになります。
また、実際に捨ててしまう行為はショック療法と呼ばれ、場合によっては心に大きなダメージを与えてします。
“おどし”を繰り返すと、子どもにどんな影響を与えてしまうのでしょうか。
- 不安やストレスを感じ精神的に不安定になりやすくなる
- 自分は価値のない人間なのではと思う
- 怒られたくないから嘘をつくようになる
もし、お子さんが友人や知り合いにおどすような言葉を使っていたと考えるとどうでしょう。「いけないことだよ」と怒りますよね。
しかし子どもは、おどす以外の伝え方がわからないのかもしれません。



“おどし”ではなく、自ら進んで片づけられるようになるための関わりが必要ですね
捨てた後の対処法
前述した通り、片づけないからとおもちゃを捨てることで、子どもの心と親子関係に深い傷をつけてしまうこともあります。
ですが、イライラして感情的になっているときに自分をコントロールすることは難しいことですよね。そしてすでに捨ててしまったのであれば、時を戻すことはできません。
捨てたり捨てたふりをした後、あなたが冷静になれたときでかまいませんので、なぜおもちゃを捨てたのか丁寧に説明し、片づけの重要性を伝えることが重要です。
また、捨てずに隠した場合、いつ出せばいいのか迷うと思います。
私もおもちゃを隠したときに、なんと言っておもちゃを戻せばいいのか悩みました。当時私が子どもを連れて通っていた、児童センターの保育士さんが教えてくれた伝え方をご紹介します。
「おもちゃを捨てようと思ったんだけど、捨てるのがもったいないと思ったから捨てられなかったんだ。Aくんにとって大切なおもちゃだよね。ママと一緒におうちに戻そう」
と言いながら一つずつ一緒におもちゃ箱に戻すと、ママもおもちゃを大切にしていることが子どもに伝わります。それと同時に片づけ方も一緒に確認できていいそうです。
あなたは神様でもロボットでもない人間です。つい感情的になってしまい、捨てるという行動に出てしまうことだってあります。



大丈夫です。そんなときは、捨てた後、隠した後のフォローを丁寧にして、片づけや物の大切さを子どもに伝えましょう
あなたは子どもにどんな風に育ってほしい?


あなたの一番根底にある想いは、【物を大事にする子になってほしい・きちんと片づけられる子に育ってほしい】なのではないでしょうか。
この想いは、子どもへの愛があるからこそです。
子どものことを想うからこそ、大人になっても片づけができないままだったらどうしよう、出したものは片づけるということを身につけさせなければと頑張ってしまうのです。
愛があるこらこその行動なのに、【片づけないなら捨てる】という方法を選んでしまうと、子どもにあなたの想いは伝わりません。
イライラすると、私もつい言い過ぎてしまいます。そして捨てるという選択をしてしまうのです。
それなら、イライラの原因を減らしてみるのはどうでしょう。イライラするのは、子どもの想いを理解できていないからかもしれません。



なぜ片づけができないのか、お子さんの気持ちを知るところから始めてみましょう!
\毎日大変でいっぱいいっぱいなママへ!立ち止まって深呼吸/
おもちゃを片づけない理由は?子どもの気持ち





自分で出したんだから自分で片づけてよ!
私も、出したおもちゃをあった場所に戻す、そんな簡単なことがなぜできないの?と、子どもたちにイライラすることがあります。
しかし、片づけない理由を知ることで、私の考えが間違っていたことに気がつきました。おもちゃを片づけない理由をあなたにも知ってほしいと思いまとめました。
- “片づける”がわからない
- 遊ぶ方が楽しい
- 上手にできたから壊したくない
- おもちゃの数が多すぎる
- 片付けられる年齢ではない
- 好奇心旺盛で集中が続かない
多くのママやパパがイライラしてしまう、子どもがおもちゃを次から次へと出して散らかす理由は、好奇心旺盛で集中力が長く続かないからです。
上記の内容についても詳しく解説していますので、気になったあなたはぜひ最後まで読んでみてくださいね!
自分とは違った想いを子どもも持っていることに気が付きます。片づけない理由を知れば、あなたの心の負担も少し軽くなるかもしれません♪
それでは詳しく見ていきましょう。
①片づけるということがわからないから
おもちゃを片づけずに放置したままにしている様子を見ると、大切にしていないのではと思ってしまいますが、決してそうではありません。
子どもが片づけないのは、そもそも“片づけ”とは何か、“どうすればいいのか”わかっていないからです。
片づけることがわからない子どもに、いくら「片づけて」と言いってもできなくて当然ですね。



2歳の息子に片づけてって何回言っても聞いてくれなくてイライラしたけど、片づけること自体がわからなかったんだ
②遊ぶ方が楽しいから


おもちゃを片づけない理由は、遊ぶ方が魅力的だからです。
片づけは、今している遊びをおわりにしなければならないため「もっと遊びたい」という気持ちが勝ってしまいます。
大人でも、趣味に没頭していたり好きなテレビを見ているときに、「おわりの時間だよ片づけて」と言われたら素直に終わらせて片づけられるでしょうか。なかなか難しいと思います。



遊びの終わりを事前に伝える、楽しく片づけをする工夫など配慮が必要ですね
③上手にできたから壊したくない


ブロックや積み木で作ったものや、情景を壊したくないという理由もあります。



息子が2~3の頃、いくら「片づけよう」と言っても行動しないので私がブロックを片づけだしたら大泣きしたことがあります
作ったブロックの作品を壊さずにとっておきたかったようです。しかし、息子は「とっておきたいから片づけたくない」と私に伝えなければならないことを知りませんでした。
理由があっても言葉で表現できなかったり、言う必要性がまだわからないこともあります。
④おもちゃの数が多すぎるから


子どもも片づけなくてはと思っていても、出したおもちゃが多すぎてどこから手をつけていいかわからずに、やる気を失っている可能性があります。
「おもちゃ片づけよう!」と私が言うと、4歳の息子は「めんどくさい」といいます。
「めんどくさい」と言うのは、パーツの多いプラレールを出したときや、細々したおもちゃを盛大に出したときが多いです。
おもちゃの量を減らすと①散らかす量も減る②片づけも簡単③子どもがやらなかったとしても大人の負担が少ないなど、メリットがたくさんあります。
⑤片づけられる年齢ではないから
イヤイヤ期がすぎた4歳頃から、自分で考え片づけられるようになります。
そのため1~3歳頃までは、片づける意味や遊んだら片づけることを子どもに教えつつ、大人がメインで片づけていくという方法でも大丈夫です。
また、4歳以降でも「面倒くさい」「遊んでいたい」と思えば、片づけられないこともたくさんあります。
親がまったく介入しなくても自分で進んで片づけができるようになるのは、6~10歳頃です。サポートしつつ片づける理由やメリットを繰り返し伝えていくことが重要です。
⑥好奇心旺盛で集中が続かない



どんどん出して、また派手に散らかしているわ
好奇心旺盛だったり集中力が長く続かないので、片づける前におもちゃを次から次へと出してしまうのです。
子どもは一つのおもちゃで長く遊び続けることが難しく、「車で遊びたいな!次は積み木!」というように好奇心のままに遊ぶおもちゃが移り変わっていきます。
年齢が低ければ低いほど集中力の続く時間は短く、成長とともに徐々に長くなっていきます。以下に子どもが集中できる時間をまとめました。
| 年齢 | 集中できる時間 |
|---|---|
| 1~3歳 | 5~10分 |
| 4~5歳 | 10~15分 |
| 6~12歳 | 20~30分 |
「散らかるから、次のおもちゃを出すなら片づけてから遊んでよ」と思うかもしれませんが、複数のおもちゃを組み合わせて遊ぶことで創造力と想像力を養うことができます。
創造力は新しいアイデアや物を作り出す力、想像力は頭の中でいろいろなことを思い描く力です。
おもちゃを片づけないに効果的な対応策8選


子どもがおもちゃを進んで片づけてくれるようになったら、あなたの負担も減らすことができますよね。
おもちゃを片づけない子どもにどんな対策したら効果的なのかまとめました。
- おもちゃの数を減らす
- おもちゃの収納を見直す
- ちらかしてもいい空間をつくる
- 片づける理由を伝える
- 片付けをゲームにする
- 遊ぶ時間のおわりを事前に伝える
- 具体的に声掛けをする
- 大人が片づける日があってもいい
まずは片づけやすい環境を整えていくことから始めましょう!
①おもちゃの数を減らす
前述した通り、おもちゃが多いと子どももママも片づけることが負担になります。おもちゃの数が多いと感じるのであれば、思い切って減らしましょう。
ここで重要なのは、絶対に子どもに内緒で手放さないということです。
しばらく遊んでいないからいらないだろうと子どもに確認せずに手放してしまうと、親への不信感や物を失う恐怖心を与え、心に大きな傷をおわせてしまいます。



必ず子どもに確認してから手放すようにしましょう
子どもに確認すると案外おもちゃの数を減らせない場合もあります。また、忙しいママにとって確認しながら手放すのは時間もかかり大変ですよね。
手放せずおもちゃの数を減らせないときにおすすめしたいのが、手放すのではなく押し入れなど見えない場所にしまっておく方法です。
- おもちゃをよく遊ぶ1群とあまり遊ばない2群に分けて、2群は押し入れなどにしまっておく
- おもちゃを3つに分け2つは押し入れへしまい、1週間や1か月など期間を決めてローテーションする
家にあるおもちゃの量は変わりませんが、部屋に出ているおもちゃの数が減るので、片づけの負担を減らすことができますよ♪
②おもちゃの収納を見直す
子どもが片づけやすい環境が作れているのかよく観察し、必要であれば収納方法を見直すようにしましょう。
現在のおもちゃの収納を確認していきます。細かく分けすぎていませんか?収納の箱はフタつきですか?
4歳ぐらいまでのお子さんだと、細かく分ける収納はハードルが高いです。また、年齢に関係なくフタつきの収納箱はフタを開けるという手間があるため【難しい・面倒】と感じてしまいます。



片づけやすいおすすめの収納方法をご紹介しますね
大きめの収納ケースにおもちゃをまとめて入れる方法はいかがでしょうか。細かく分けずにまとめることで、子どもも片づけのハードルがぐんと下がりますよ。
また、おもちゃをいくつかのケースに分けて収納する場合、どこにおもちゃを片づけたらいいのか一目見てわかるように、写真やイラストを貼る方法もあります。
上記の方法なら、どこになにがあるのか一目でわかるので、“どこにしまったらいいかわからない”を防ぐことができます。
初めの準備は大変かもしれませんが、片づけに慣れてくれば一人で片づけができそうですね。
③散らかしてもいい空間をつくる
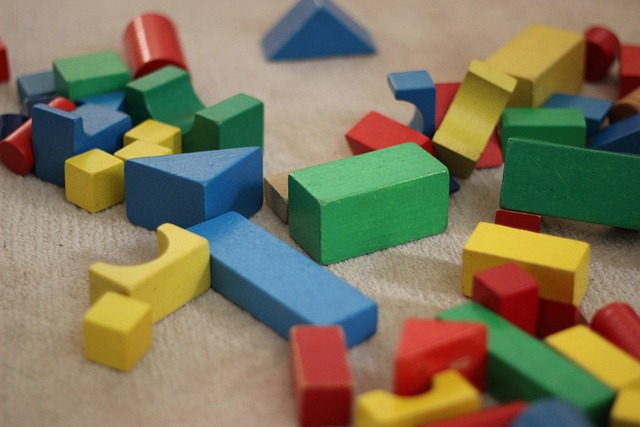
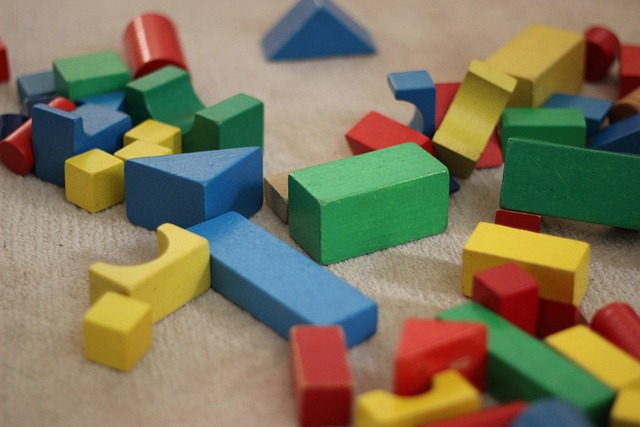
どれだけ散らかしても良い、おもちゃの部屋や遊ぶスペースをつくることでママの心の負担を減らすことができます。
私も実践し心の負担が減りました。将来息子が使う予定の子ども部屋をおもちゃの部屋にし、どんなに散らかしてもいいことにしました。
ただしリビングは一日の終わりに片づけるようにしています。子ども部屋はぐちゃぐちゃですが、いつもいるリビングはきれいに保てているのでストレスがありません。
部屋を用意できないとすれば、リビングの一角にプレイマットや布などをひいて遊ぶスペースをつくるのはいかがでしょうか。
遊ぶスペース内は片づいてなくても良いルールにします。そうすれば、部屋中に散らばったおもちゃをスペース内に入れるだけで片づけが完了します。



あなたが「まあいいか」と思える、散らかしてもいいスペースをつくってみてください
④片づける理由を伝える


大人からすると、片づけるのが当たり前という感覚がありますよね。しかし、子どもは片づいていた方が良い理由がわかりません。
片づけないとどんな嫌なことが起こるのか、片づけたらどんないいことがあるのかわかっていれば、自分から進んで片づけをするようになります。
片づけないとどんなことが起きる?
- おもちゃを踏んで痛い思いをする
- パズルのピースがなくなって完成できない
- 探しているおもちゃがみつからない
片づけるとどんなとが起こる?
- おもちゃを踏むことがないので痛い思いをしない
- パズルのピースがなくならないから完成させられる
- おもちゃの“おうち”を決めておけば、探す時間が少なくてすむ
- 部屋が片づくときれいで気持ちいい
上記の例は、特に足で踏んでしまって痛がっているとき、おもちゃの一部がなくなってしまったときに繰り返し伝えることで子どもも納得していきます。
また、片づけた後に、きれいになった部屋がきれいで気持ちいいことを伝えましょう。繰り返し伝えることで、片づけると部屋がきれいになり、いいことがあるんだと感じてくれます。
⑤片付けをゲームにする
遊ぶ方が楽しいと思っている子どもには、ゲームのように片づけをするのが効果的です。
片づけをゲームのようにするアイディアをご紹介します。



テンポの良い曲を片づけ用のBGMと決めて、曲が流れただしたら片づけるようにしています



上の子用・下の子用・ママ用に箱を分けて競争してます
言葉で「片づけの時間だよ」というよりも、音楽は子どもに耳に入っていきやすいです。特に楽しげなアップテンポの曲だと、なおさら反応してくれるでしょう。
片づけの時に流れる曲が決まっていれば、条件反射で片付けをしてくれること間違いなしです!
⑥遊ぶ時間の終わりを事前に伝える


いつまでも遊んでいたい子どもにとって、突然の片づけは受け入れがたいものです。
遊ぶ時間の終わりを事前に伝えることで、子どもも心の準備ができます。心の準備ができていると納得して行動してくれることにもつながります。
大人は、19時にお風呂に入るならそれまでにご飯を食べて片づけないとなど、時間を見越してやることを考えられますよね。
しかし、時間を見越して考え、行動できるようになるのは9~10歳頃です。
ご飯の前や寝る前など片づけてほしいタイミングがあれば、あとどのぐらい遊べるのか事前に伝え、終わりを明確にすることで子ども自身も心の準備ができますよ。



時計がまだ読めない年齢は、あとどのくらい遊べるのか視覚的にもわかりやすい実感タイマーがおすすめです


実感タイマーとは、時間の経過が色でわかる商品で、時計が読めなくても10分がどのぐらいなのか目で見てわかります。
時間がきたらタイマーが鳴るので終わりがわかりやすく、遊ぶ時間にメリハリをつけるときにも効果的です。
\時計が読めなくても、あと10分が目で見てわかる!/
⑦具体的に声がけをする
片づけを促したいときは、必ず「何」を「どこに」戻してほしいのか、具体的に伝えるよう意識しましょう。
「お片付けしようね」ではない具体的な声がけをご紹介します。
- ブロックを緑色の箱に戻してくれるかな?
- 次はぬいぐるみをこの袋に入れよう!
「何」を「どこに」としっかり伝えることで、子どもは迷わず行動に移すことができます。そして言葉の情報と実際の行動が合わさり、ブロックは緑色の箱なんだと記憶に残りやすいのです。
1回や2回では覚えることは難しいので、繰り返し具体的に伝えていきましょう。
⑧大人が片づける日があってもいい
子どもの出したおもちゃを大人だけが片づけていたら、片づけをしない子になってしまうのではないかと心配になりますよね。
片づけさせなければと頑張らなくても、かわりに大人が片づける日があっても大丈夫です。
片づける理由やメリット、片づけ方を繰り返し伝えていけば、無理に片づけさせなくても自分で片づけられるようになる日がきます。
私は片づけが得意な方なのですが、子どもの頃から母に片づけるよう言われたことが一度もなく、母がすべて片づけをしてくれていました。
しかし、物心ついた小学校高学年ぐらいの頃には自分の机は自分で片づけるようになっていました。片づけると机の上がきれいになって気持ちいいことを知ったからです。



片づけのメリットがわかっていれば成長とともに身に付きます
まとめ


- 子どもがすすんでおもちゃを片づけるようになるためには、捨てたり捨てたふりをするのではなく、片づけることのメリットや理由を伝え一緒に取り組むことが大切
- おもちゃを捨てられた経験から、大事なものなら片づける必要があることを学ぶ場合もあるが、心と親子関係に傷がついてしまう可能性も高い
- 片づけないという理由で捨てることを繰り返すと、子どもは精神的に不安定になりやすかったり、自己肯定感が低くなってしまう
- 捨てた後の対処法としては、あなたが冷静になってから、なぜおもちゃを捨てたのか子どもに丁寧に説明し、片づけの重要性を伝える必要がある
- 子どもが片づけない理由は①“片づける”がわからない②遊ぶ方が楽しい③上手にできて壊したくない④おもちゃが多すぎる⑤年齢的に難しい⑥集中が続かない
- おもちゃを片づけない子どもへの対策として環境の整え方は、①おもちゃの数を減らす②おもちゃの収納を見直す③ちらかしてもいい環境をつくる
- おもちゃを片づけない子どもへの関わり方は、④片づける理由を伝える⑤片づけをゲームにする⑥遊ぶ時間の終わりを事前に伝える⑦具体的な声がけをする
- 子どもに片づけさせなければと思いがちだが、ママやパパが気が楽になるのであれば⑧大人が片づける日があってもいいというのも対策のひとつ
片づけは多くのママが抱えている悩みです。自由に遊んでほしいという想いはあるけれど、片づけの大変さがつきまといますよね。
実際に捨てたことのある方の体験談を知ることで、おもちゃを捨てることは効果が少ないのだと改めて感じました。
片づけないからとおもちゃを捨てる・捨てたふりをしてしまうと、あなたが一番伝えたい【物を大事にできる子になってほしい】という想いが伝わりません。
それどころか、子どもの心と親子関係に傷を残してしまうこともあります。
私はあなたに、“子どもに片づけさせなければ”と頑張らなくていい、ということを伝えたいです。
片づけをすると、部屋がきれいになって気持ちいいというメリットや片づける理由を繰り返し伝え、あなたがお手本を見せていれば自然と身についてきます。
ご紹介した内容を参考が、あなたのイライラと片づけの負担を少しでも減らす手助けとなれたらうれしいです。











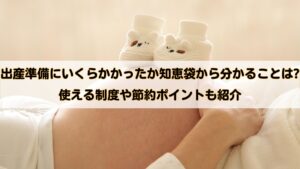
愛情を注がれた子-特徴-保育園-300x158.jpg)
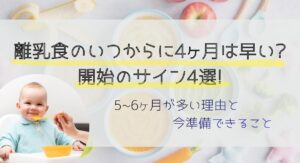

コメント