 私
私私は小2と年中の2児の母です。 養護教諭の勤務歴があり、保健室では勉強が苦手な子と関わることもありました。
小学校高学年以上になると、親への反抗心も芽生え、 通信教育や塾、生活のルール作りなど、さまざまな工夫をしても勉強習慣が身につきにくくなりますよね。
下がる成績に「もう見捨てる覚悟で突き放すしかないのかな…」と悩んでいるお母さんも多いのではないでしょうか。
調べてみたところ、勉強をしない子でも見捨てるのではなく、お子さんに合わせた学び方や親のサポートで学びを深められることが分かりました。
- 勉強をしない子を見捨てる以外の方法
- 勉強が必要な理由とこれからの時代に求められる学び方
- 勉強をしない子の特徴
- 親ができる効果的なサポート方法3選
「何をしても勉強しない!」というイライラから解放され、家族で笑顔で過ごせる日々の参考にしていただければ幸いです。
\勉強嫌いだったお母さんに、おすすめの一冊/
勉強をしない子は見捨てるしかない?





反抗期に入って、全く勉強しない子に。言っても聞かないし、勉強は見捨てるしかないのかな…
通信教育や塾、生活のルール作りなど、何を試しても勉強しない子を見ていると「見捨てる方が子どものためになる?」と思ってしまいますよね。
勉強をしたがらないお子さんでも、見捨てるのではなく、本人の好奇心や理解に合わせた学びは必要です。
国連の「子どもの権利条約」や日本の教育制度では「教育を受け学ぶことは、すべての子どもの権利」であると定められています。
- 学びは「テストの点」や「進学」のためだけでなく、「よりよく生きるための基礎」として必要
- 勉強をしない子でも「その子らしい学びの形」が必ずあり、それを周囲の大人や社会が支えることが大切
すぐに調べられるネット端末があり、働き方も多様化する中で、知識を身につけることに意味があるの?と思うお子さんやお母さんも増えているのではないでしょうか。
国連や日本の義務教育の中で示されている「学び」には教科の勉強で身につく「知識」「思考力」の他にも、以下のようなさまざまな能力を育むことが示されています。
- 感情をコントロールする力
- さまざまな立場の人と関わる力
- 集団で協力する力
- 社会のルールを理解し守る力
- 多様な意見に触れ尊重しあう力
ここからは勉強の必要性や、これからの時代に求められる学びについて詳しく見ていきましょう!
勉強はなぜ必要?
養護教諭経験から得た私の意見は「多くの時間を過ごす授業についていけない=お子さんが苦痛に感じる時間が増える」ため勉強は必要です。



算数だけが苦手で「将来使わない数学の公式をどうして勉強しないといけないの?」と聞かれて返答に困りました…
お子さんに「必要ない知識をどうして覚えなきゃいけないの?」と聞かれてお困りのお母さんは、さまざまな勉強をする意味もぜひ参考にしてください。


- 頭と手先のトレーニング(記憶力、思考力、手順通りに実行する力)
- 選択肢を広げる(今は使う予定はなくても、将来やりたいことができた時に必要な知識になるかも)
- 得意なことを見つけて仕事や生活に活かす
- 苦手なことへの向き合い方を学ぶ
余談ですが、思春期は不登校も増える時期です。
不登校というと、「集団になじめない」や「友人関係のトラブル」を思い浮かべるお母さんが多いのではないでしょうか。
実は、養護教諭時代の実感では「授業についていけない」が常態化しているお子さんに、何かのきっかけが重なって休みがちになるパターンが多いと感じています。



保健室で勉強が嫌いなお子さんに出会ったら、必ず「好きなこと」を聞いていました。
勉強が本当に苦手でも、自分の「好き」「得意」を生かして、クラスの中で存在感を発揮できたお子さんもたくさんいます。
これからの時代に求められる勉強、学びについても見ていきましょう!下の「勉強しない子の学び方」についてもぜひ参考にしてください。
これからの時代に求められる勉強とは?
学校教育でも通常の授業の他に「キャリア教育」や「アクティブ·ラーニング」という教科の枠にとらわれない、主体的な学びが重要視されています。


<キャリア教育>
- 一人ひとりが社会的·職業的に自立できるようになるための能力や態度を育てる教育のこと
- 仕事に関する知識やスキルを身に付けると同時に、「自分らしい生き方」や「働く意義」について考える力を養う
- 将来の進路や生き方を自分で考え、選択できる主体性を育てることを目指す


<アクティブラーニング>
- アクティブラーニングは、子どもたちが「自ら能動的に学ぶ」ことを目的とした学習の方法
- 受け身の授業ではなく、話し合いや調査、問題解決など、子どもたちが主体的に考え、行動しながら学ぶ
- 単なる知識の習得だけでなく、「考える力」「社会的スキル」「協力する力」など、さまざまな能力を育むことを目指す
(参考元:文部科学省|新しい学習指導要領等が目指す姿)
親世代が子どもだった頃より、学校教育も単なる知識の習得にとどまらず、将来にわたって活かせる力を伸ばす方向にシフトしていることがわかりますね。
苦手は見捨てるのではなく「見守る」「切り替える」
新しい学習指導要領では、これからの教育は「苦手」を個性の一部として受け入れ、得意や強みを伸ばすことを重視することが示されています。
苦手科目への関わり方は、①克服できる程度の苦手なら減らす②克服が難しい苦手はいったん見守り、得意分野の頑張りに切り替えるという2つの方法が考えられるでしょう。
「苦手だからやらない」と最初からあきらめてしまうことは要注意ですが、「苦手の程度を知り、克服することにこだわらない」は大切な視点ですね。
子どもは、その年に理解することが難しくても、翌年には理解できる場合もあります。



克服できそうか、見守るべきかはどうやって判断したらいいの?
私の経験上での大まかな見分け方をご紹介します。
まだ素直に話してくれるお子さんの場合は、お子さんに「勉強難しい?」「今、算数で何やってるの?」「どこが分からない?」など聞いてみましょう。
<克服できそうなサイン>
- 素直に「難しい」「できない」と言える
- どの単元をやっているのかや大まかな内容は把握している
- どこが分からないのかを話せる
<見守りや切り替えのサイン>
- それ以上聞かれないように「大丈夫」と漠然とした返答をする
- テストやノートは見せない
- やっている単元を把握していない
- 何が分からないかも分からず、話せない
子ども本人が話したがらないときは、授業中の様子や成績について通知表や個人懇談、連絡ノートなどを活用し、担任の先生に確認してみましょう。
「学校に行き渋るようになった」など急を要する場合は、個別に面談の時間を作ってもらうこともできます。
\算数が苦手なお子さんの復習に!/
勉強しない子に合わせた学び方とは?



学校での勉強も変わってきているのは分かったけど、子どもに合わせた学びのイメージがつかない…
子どもに合わせた学び方には、「興味ベースの学び」「学び方の工夫」があります。
学び方の具体例を以下に示しますので、参考にしてください。


<興味ベースの学び>
- 昆虫好きな子が虫取りを通じて虫の観察、生物の環境について学ぶ
- ゲーム好きな子がプログラミングやロボット作りを通じて数学や論理的思考を学ぶ
- 撮り鉄の子が写真の撮影スキルを活かして学校行事の写真撮影をする
- 絵やイラストの得意な子が調べ学習の図を担当したり、文集の表紙を書く


<学び方の工夫>
- 読み書きが苦手な子がデジタル機器の読みあげ機能やタイピングを使って効率良く学ぶ
- 動画教材や学習アプリを活用し、苦手な学習内容の復習を繰り返す
- ボランティアやアルバイトを通じて、人との関わり方や感謝される喜びを学ぶ
子どもの興味や得意·不得意に合わせて「こんな学び方もアリ」と認めることが、「その子らしさ」を生かした学びの形へとつながります。



わが家ではこの夏休みにクレーンゲームが大好きな息子とクレーンゲームのアームを工作しました!
親が勉強と思っていないことでも、子どもはさまざまなことを観察し気づきを与えてくれます。お子さんの興味に付き合う夏休みにしてみましょう!
勉強しない子の特徴4つと対処法
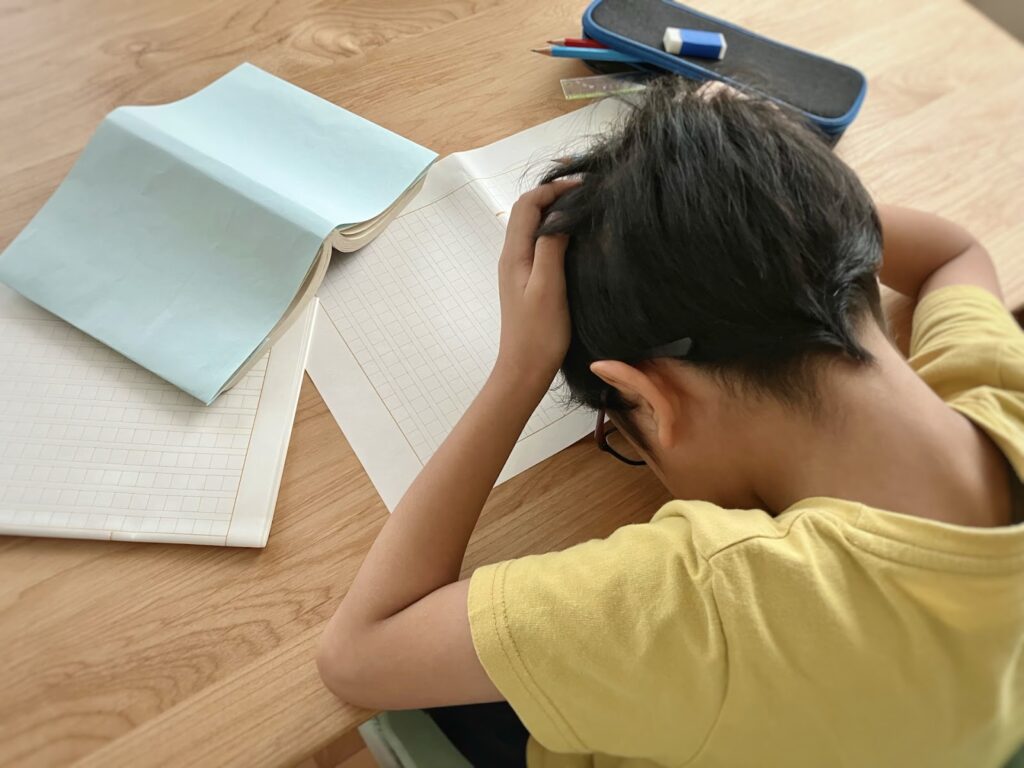
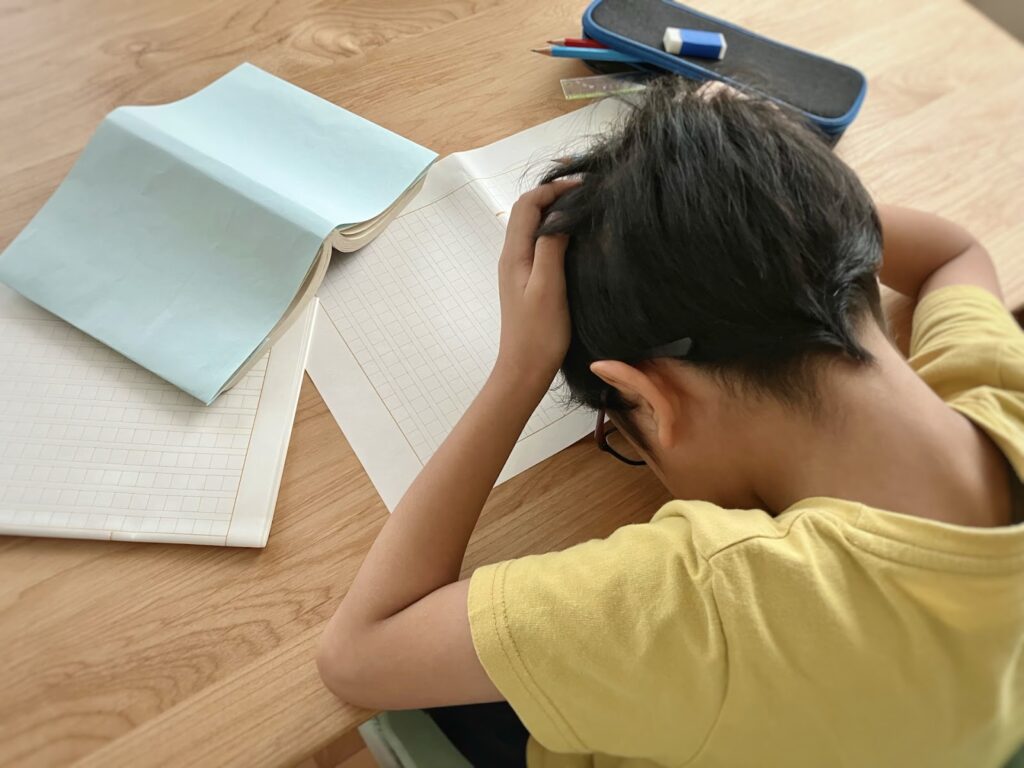
勉強しない子の特徴には①集中できない②勉強のやり方がわからない③勉強する意味が分からない、しなくても困らない④親への反抗があります。



うちは親への反抗かな…成績が下がっても困ってないのもありそう
勉強しない子の特徴について、その背景や対策を解説していきますので、お子さんに当てはまるものがあれば、ぜひ対応の参考にしてください。
①集中できない
やっと机に向かったと思ったら、スマホの通知音ですぐに勉強を中断したり、「わかんない」とあきらめてしまったりする様子はありませんか?
集中できない場合は「集中するのが苦手」「勉強以外にやりたいことがある」などの原因があり、そばに不要な物を置かない、スマホの電源を切るといった環境整備が大切です。
他にも、さまざまな理由や対策が考えられますので、以下を参考にしてください。


- もともと集中するのが苦手
- 視界に勉強道具以外のものを置かない
- 10分ほどの短時間から勉強する内容を限定してやってみる
- 読み上げ機能など子どもが理解しやすい方法を活用する
- スマホ、ゲーム、友達とのLINEなど、他にやりたいことがある
- スマホやゲーム使用のルールを見直す
- 勉強中はスマホ、ゲームの電源を切り、勉強後のごほうびとして使用時間を決める
- 寝不足や空腹、疲労がある
- 食事や睡眠の基本的な生活習慣を整える
- 疲れていても10分は勉強する
- 悩みがあり、勉強が手につかない
- 悩みの解決や相談をして気持ちを落ち着かせる
- 悩んでもどうしようもないことは気分転換をする
集中が持続しないお子さんに最初からまとまった時間の勉強は難しいため「1回10分でOK」「やらないよりはいい」と捉えましょう。
\集中力トレーニングの定番!/
\難易度の調整ができるぐらぐらゲームもおすすめ!/
②勉強のやり方がわからない
やり方が分からないことに取りかかるのは大人でも大変ですよね。すでに苦手意識があるなら、なおさら行動へのハードルは高くなります。
勉強のやり方が分からないお子さんに最初から問題集をやるように言っても、できないのは当たり前です。
やり方が分からないお子さんの場合も、以下のように小さなステップで「できた」を積み重ねていきましょう。
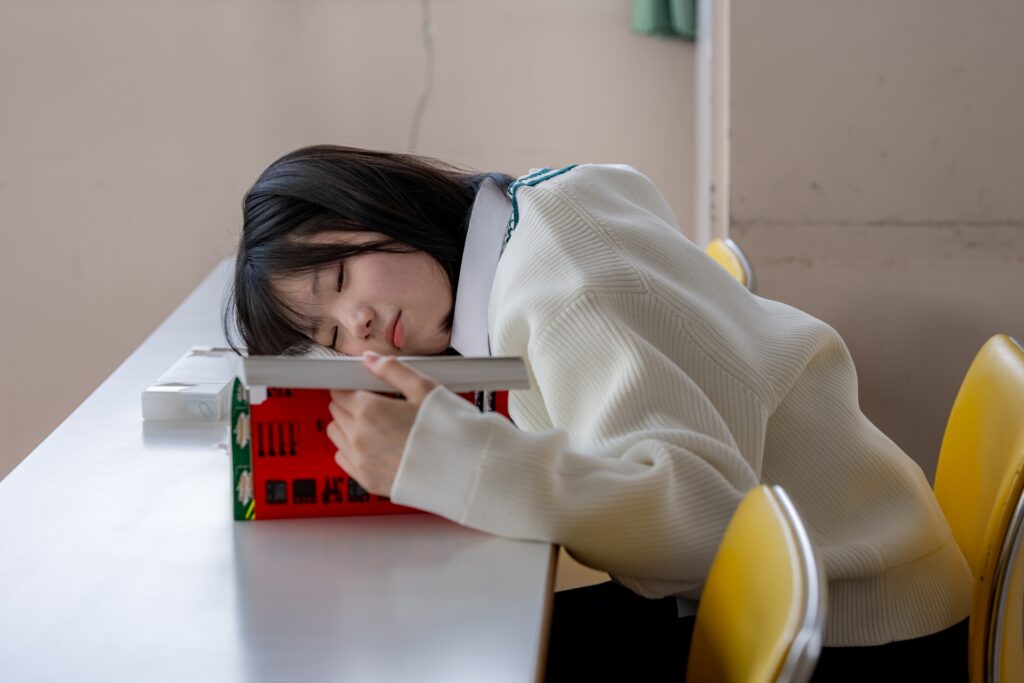
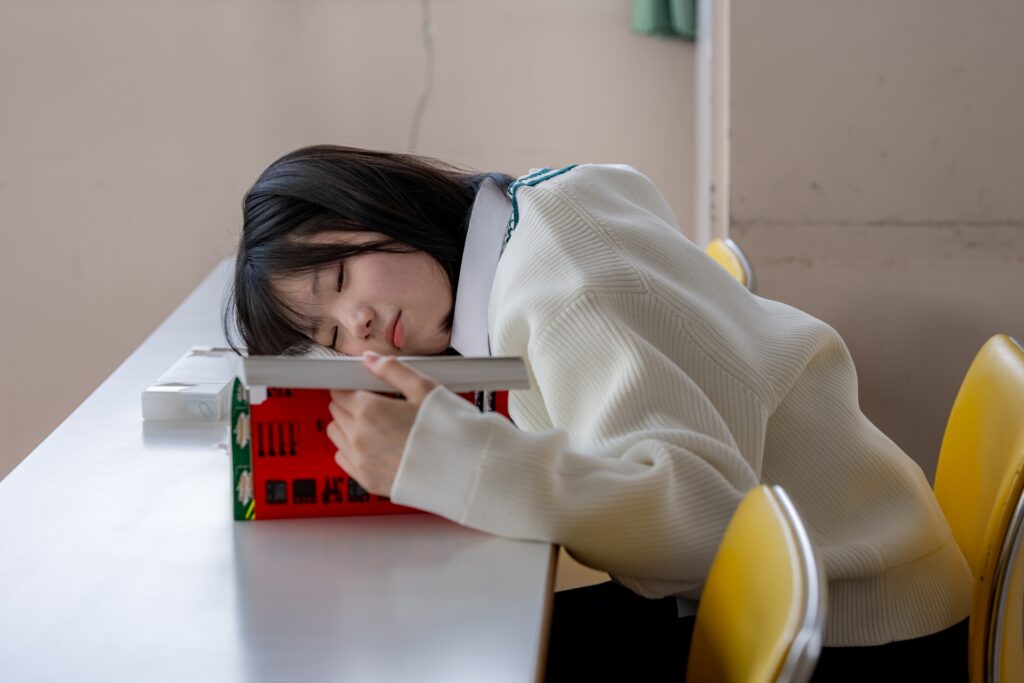
- 勉強に必要な道具を出す
- 漢字や英単語の練習、簡単な計算問題など、やり方を考えなくてもできるものから始める
- 手を動かしているうちにやる気が出てきたら、簡単で少ない問題数のプリントから始める
- やる気が出なければプリントはしなくてもOK
簡単なプリントは以下のサイトからダウンロードすることができますよ。
\幼児~小学3年生まで/
\幼児~中学生まで/
\こちらにも参考になる勉強法を掲載しました!/


③勉強しなくても困らない
YouTuberなど、学歴不問の職業も認知されている昨今、勉強をしないことで将来に不安を抱くお子さんが減っているのではないでしょうか。
知識がなくても、手元にはなんでも調べられるスマホがあり、自分で覚えておかなければ困るという状況も格段に減っていますよね。
生活や将来で困ったり、不安になったりすることがないことが勉強の意味を見出せない要因になっています。
勉強を自主的にする子の大きな特徴に「目標がある」がありますが、裏を返せば、しないと目標が達成できず、困る状況があるのです。



勉強をしないことで困ることを伝えたらいいの?


- やらせようとすると余計にやらなくなるのが反抗期
- 困っていないのはある意味幸せなことと捉える
- 生活リズムやスマホのルールは守らせて
- 困らせるのではなく、勉強で得られる良さを伝えて
- 好きなことを一緒に楽しむ
- 子どもがつまずいたり、目標を見つけた時が勉強の始めどき
- 子どもの目標は大人が想定しないところからやってくることもあるので、気長に、縁を待つ
勉強で得られるメリットはご褒美でもいいのですが、お金や物ではなく「宿題やったら、おいしいアイス屋さん行こう」など、楽しい体験の共有がおすすめです。
④親への反抗
今やろうと思っていたことを親から「やりなさい」と言われて、腹が立ち、結局やらなかったという経験は誰しもあるのではないでしょうか?
反抗期や思春期には、「自分で決めたい」「縛られたくない」という気持ちが強まるため、親が何気なく言った言葉でも反発し、やらなくなってしまいます。



言わなくても勉強しないから、つい言ってしまう…
「先に勉強しなさいよ~」と毎日のように声をかけてきたお母さんにとっては、クセになっているセリフですが、命令調の声かけを減らす意識が大切です。


- 門限やお小遣い、スマホ使用など最低限の生活ルールはぶれさせない
- 言っても聞かないなら言わない方がいい
- 反抗期が終わったら、また素直に話せると信じて待つ
- 反抗期が終わるまで、命令調の声かけは封印
- 子どもから話しかけてきたときや相談があったときは丁寧に応じて
- 親が決めるのではなく、子どもに決めさせる



私も自分の子どもでは未経験なので、しっかり覚えておきます!
次に勉強しない子の親の関わりについて、より詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
勉強をしない子の親ができるサポート3選


勉強をしない子に親ができるサポートとして①子どもの良さを見つける②可能な範囲で生活を整える③親も一緒に学ぶをご紹介します。
一見、関係がないサポートに感じるかもしれませんが、思春期や反抗期は「勉強」と口に出しただけで反抗心をあおってしまいます。
勉強とは直接関係がないところでお子さんのやる気をアップさせたり、集中しやすい土壌を育むことで、学びにつながることも期待できるでしょう。
生活に取り入れられそうなものがあればぜひ取り組んでみましょう!
①子どもの良さを見つける
お子さんのいいところに1つでも気づくことは、勉強をしない子でも「まぁ、いいか」とおおらかに見守れる第一歩です。
アイムフリーさんの親も気づいていない子どもの良さを伝えるX投稿にとても共感し、掲載させていただきました。
実際に「勉強も運動もしない子でなんの取り柄もなくて…」とおっしゃるお母さんに私も数多く会ってきました。
「うちの子の良さが分からない…」というお母さんはぜひ、担任の先生や習い事の先生、友人、親戚など、客観的にお子さんを見ている人に聞いてみましょう!



そして、日常の中でさりげなく「君のそういうところがホントいいよね!」と伝えてあげてくださいね。
表面上は「キモっ!何言ってんの?」と言われるかもしれませんが、褒められて嬉しくない子どもはいません。照れ隠しで強気に反応しているだけですよ。
②可能な範囲で生活を整える
反抗期になると、夜更かしをして、朝はギリギリに起きてきて「朝ごはんいらない!」と言われる日も増えていきますよね。
親の管理が行き届きにくくなりますが、食べない日が続いても食事は毎日用意するなど、いつでも規則正しい生活に戻れる準備は整えてあげましょう。



朝の保健室には飲まず食わずで走ってきて貧血になった生徒が時々来ましたね。
多分、お子さんは朝ごはんを食べずに貧血になり、保健室で休んだ話など親にはしないと思いますが、「やっぱり、ちゃんと食べよう」と思うでしょう。
お子さんの「いらない」「ほっといて」を受け止めつつ、必要な時はいつでも戻れる準備をしてあげてくださいね。
\スマホルールは緩めずこちらをチェック!/


③親も一緒に学ぶ
親自身に勉強への苦手意識があると「面倒なことは先に終わらせて…」など、ふとした言葉の中にネガティブな表現が出てしまいますよね。
親が嫌な顔せずに子どもの勉強に付き合ったり、学ぶ姿を見せると、子どもが学ぶことにネガティブなイメージを持ちにくいと言われています。


- 子どもが宿題をしている隣で親も読書をする
- 家族で図書館に行く
- ニュースを一緒にみて家族で話す
- 親が学んでいることを家族で話す
勉強が苦手なお母さんでも、お子さんと一緒に悩んだり、間違いを笑い合って過ごした時間はお子さんにとって楽しく、記憶に残る勉強時間となるでしょう。



わが家は私が記事の調べものをする横で子どもが勉強をするのが日課になっています。
\大人も一緒に勉強しよう!/
まとめ


- 勉強をしない子でも、見捨てるのではなく、本人の好奇心や理解に合わせた学びが必要
- 「多くの時間を過ごす授業についていけない=子どもが苦痛に感じる時間が増える」ため子どもの充実した生活のために勉強は必要
- 学校教育でも「キャリア教育」や「アクティブ·ラーニング」という教科の枠にとらわれない、主体的な学びが重要視されている
- 苦手科目は見捨てるのではなく、いったん見守り、得意分野の頑張りに切り替えるという視点が大切
- 子どもに合わせた学び方には、「興味ベースの学び」「学び方の工夫」
- 勉強しない子の特徴は「集中できない」「勉強のやり方がわからない」「勉強しなくても困らない」「親への反抗」がある
- 勉強をしない子に親ができるサポートとして「子どもの良さを見つける」「可能な範囲で生活を整える」「親も一緒に学ぶ」をご紹介
「さまざまな対策を調べてやってみても、全然勉強をしない…いっそ見捨てる覚悟で突き放すべき?」 とお悩みのお母さん、反抗期のお子さんへの対応、本当にお疲れ様です。
お子さんの好きなことや得意なこと、「ほっといて!」という思いに寄り添う姿勢は、決してわがままにさせるわけではありません。
なかなか素直に謝ったり、お礼を言ったりできないだけで、お母さんがお子さんを思う気持ちは伝わっています。
お子さんが本当に困ったときに頼れる安全基地となり、お子さんの良さを伸ばせるように、この記事を参考にしていただければ嬉しいです。


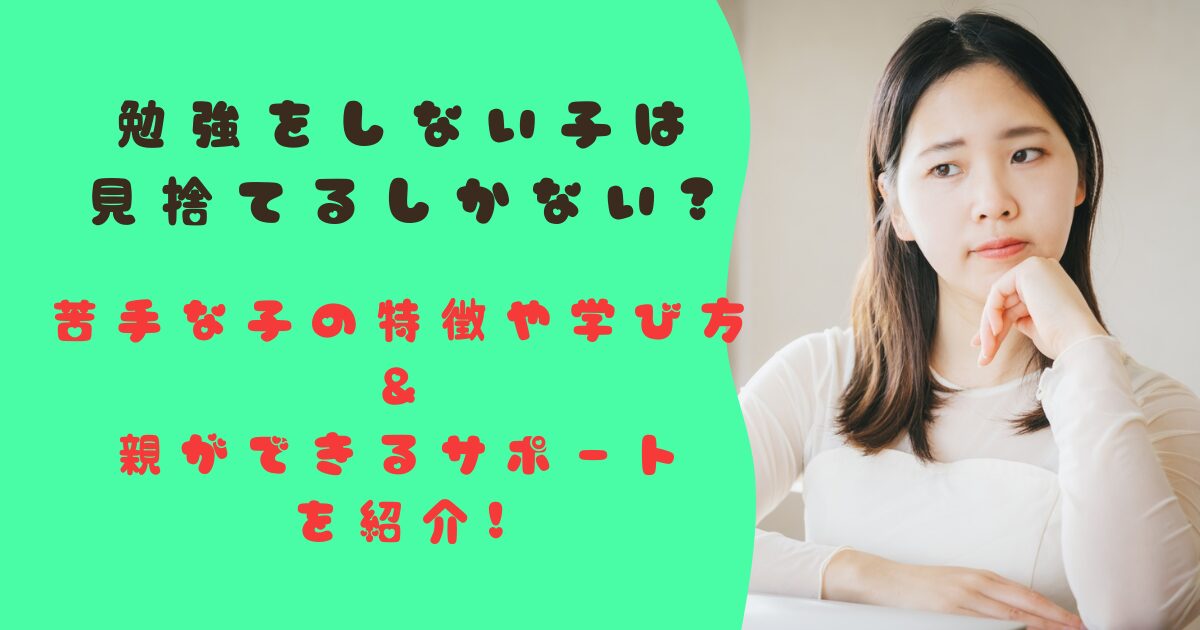




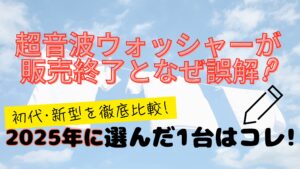
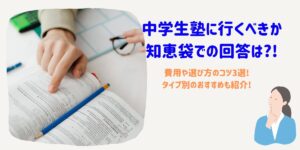

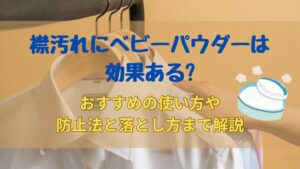

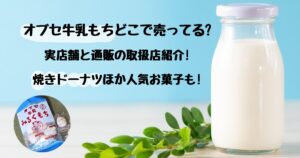

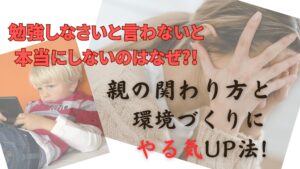
コメント