 私
私私はパート勤務で、小5の息子と小2の娘がいます。
ママ友と「勉強しなさいと言わない子育て」についてよく話題になり、実践している方も多いと思います。
私も言わないようにして見守りますが、子ども達は帰宅後すぐにゲーム、勉強を本当にしないです…。



勉強しなさいと言わないのに、どうして本当にしないの?
イライラと不安がつのり、詳しく調べてみました。
子どもの脳はまだ発達の途中にあり、今やるべき事よりも目の前の楽しさを優先するため、勉強や宿題は後回しになるのです。
- 勉強しなさいと言わないのになぜ本当にしないのか
- 言わない親の葛藤と関わり方
- 家で学ぶための環境づくり
- 勉強のやる気と楽しさを一緒に育てていく方法
言わないと勉強を本当にしないお子さんを抱え、勉強しなさいと言いたくないあなたは、ぜひ最後まで読んで、勉強しない状況を変えていくきっかけにしましょう。
\頭ではわかっていても、「●●しなさい!」が我慢できない/
勉強しなさいと言わないと本当にしない現実と理由





勉強は子どもの自主性に任せてきました。気づけば、本当にしないんです。「勉強しなさいと言わない」ことは、「放っておく」ことと同じですか?
SNSやブログや本で「勉強しなさいと言わない子育て」が良いとされているのを目にし、言わないようにしていたのに、この違いは何でしょうか。
子どもの脳はまだ未熟で、宿題など今やるべきことを選ぶ力が弱いため、宿題を後回しにしてしまいます。「見守る」つもりが、結果としてただ放っておくことになっているのです。
不安を感じ始めた悩むママに、同じような葛藤をもつ私の視点から、「勉強しなさいと言わないと本当にしない」その現実と理由を見ていきます。
言わないと本当にしない我が子の現実
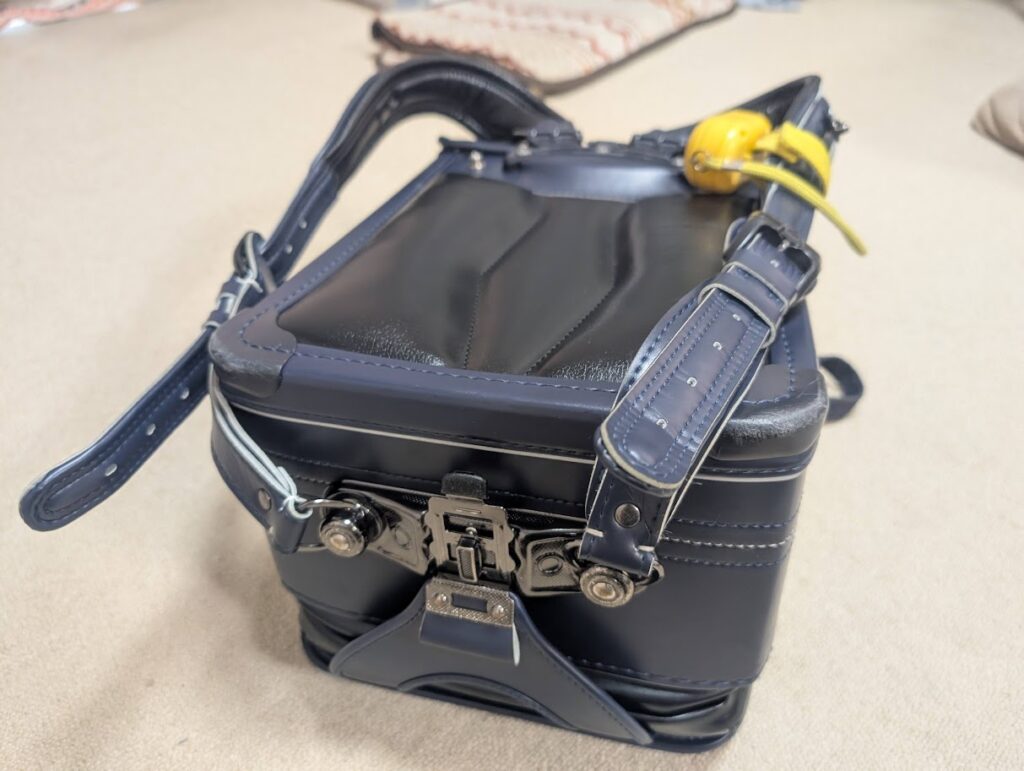
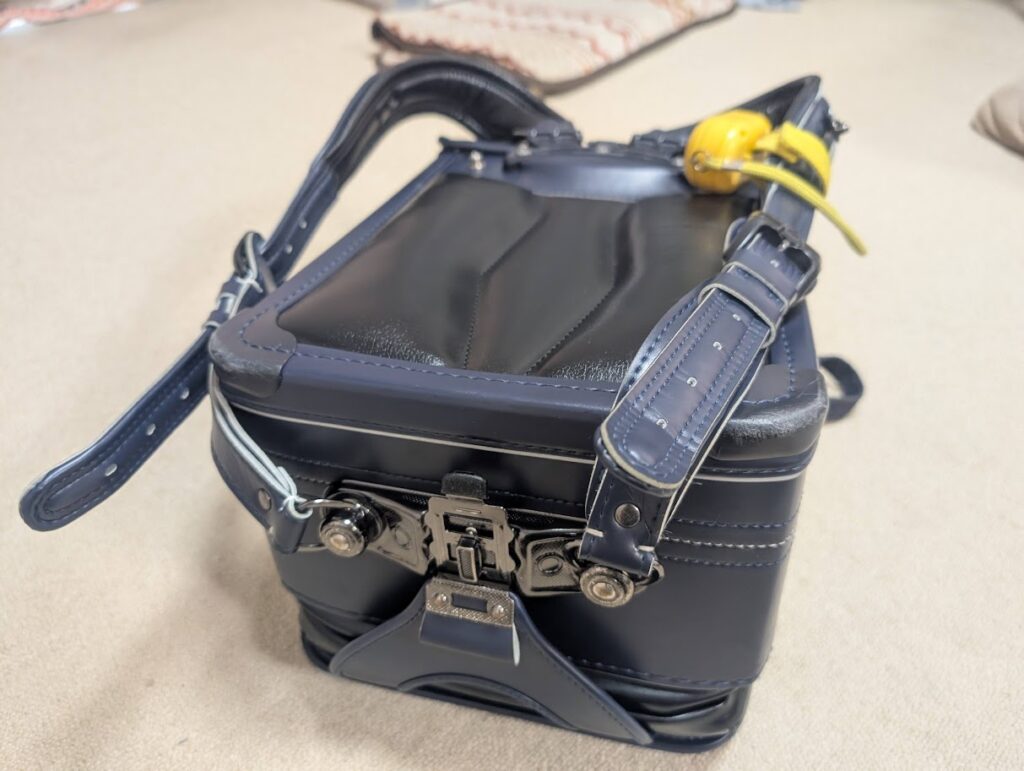
現実は、私が仕事から帰るとランドセルは放り出され、子ども達はゲームに夢中。宿題に手をつける気配はありません。ランドセルを開けた形跡すらない…。
私自身、子どもの頃に勉強のことで毎日叱られて反発した経験があり、子どもには「自分で気づいて動く力」を育てたいと思ったのです。



「勉強しなさい」と言わない子育てをしたくて。でも、本当にしないんです…
口を出さず、手をかけすぎず、見守ることが自立に繋がると信じていました。しかし、現実はうまくいきませんでした。
夕食の準備をしながら、小2の娘は宿題を広げて「これ読んで〜」と話しかけてくる一方、小5の息子はゲームから目を離そうとせず、声をかけても気づかないふり。
毎日「見守る」つもりでいましたが、私の中にあったモヤモヤが、息子へのイライラに変わっていました。そして、ついに言ってしまったんです。



宿題してないでしょ!
ゲーム止めて、勉強しなさい!



うるさいな!なんで急にそんなこと言うんだよ!
今からやろうとしてたんだよ!
やってしまった…。家の空気は一気にピリつきました。できれば、もうこんなふうに怒りたくありません。
言わないとしない、言うと怒る、見守れば放っておいたことになる…。葛藤の中、「本当はどうすればよかったんだろう?」と立ち止まって考えました。
なぜ勉強しなさいと言わないと子どもは本当にしないのか、もう少し深く見ていきましょう。
言わないと本当にしない理由
親としては、「先に宿題を終わらせて、後でゆっくり遊べばいいのに」と思いますよね。しかし、目の前の子どもはゲームに夢中、宿題なんて頭にない様子…。
なぜこんなことになるのでしょうか?
子どもはまだ「今やるべきこと(宿題)」と「今やりたい楽しいこと(ゲーム)」を比べて、今やるべきことを判断して選ぶ力が弱いため、今やりたいことを我慢できずに優先してしまうのです。
大人が「後で困るから今やっておこう」と判断できるのは、脳の「前頭前野」がしっかり働いているからです。
脳の「前頭前野」とは?
前頭前野は「自制心」や「計画性」を管理する脳の一部分ですが、この発達はイヤイヤ期の2歳頃から始まり、なんと25歳前後まで続くと言われています。
子どもの脳はまだ発達の途中であり、親が「勉強しなさい」と言わずに見守っても、「今やりたいこと」を優先するのが多いのはこのためです。
言わなくても動ける子は「前頭前野の発育が進んでいる」「性格的に真面目」「親が環境を整えている」など、いくつかの条件が揃っていることが多いですよ。
どうして子どもは「勉強しなさい!」と言われて反発するの?
宿題をしていなかったから怒られた、と思ったからでしょうか?そう単純な話しではありません。
子どもが反発してしまったのは、「なぜ今まで当たり前にしていたことで急に怒られたのか」理由が分からずに、混乱したからです。



今まで何も言われなかったのに、急に勉強しなさいって怒られた!何なんだよ!
親としては「見守るつもり」でも、何も言わずにただ静かにしていると、子どもには「無関心」と受け取られてしまうこともあります。
子どもはどこか寂しさや不安、そして怒りを感じていたのかもしれません。
子どもは「やりたくない」のではなく、目の前の楽しさを優先してしまうため、「その内気づいてやるだろう」ことはほとんどなく、やらないままになるのが現実です。
では、どうすればいいのでしょうか?親としては、勉強をする力や習慣を少しずつ育てていきたいですよね。
次は、「勉強しなさい」と言わずに関わるために、親が実践できる関わり方や工夫をご紹介します。
\これを読むと、自分から勉強する子になるのは時間の問題に!?/
勉強しなさいと言わない親の葛藤と関わり方の工夫3選


「勉強しなさい」と言わないと決めても、親の心の中は複雑です。
親は勉強しなさいと言わない気持ちと本当にしない焦りやイライラで葛藤を抱えます。言わない代わりにどう関わるか、無関心ではなく信頼して見守る距離感が大事です。



勉強しなさいと言わないことは、ただ見守るだけでも、放っておくことでもないんですね。そこが分かりませんでした。
ここでは、言わないと勉強しない子どもにどう関わるのがいい距離感なのか、親子の関係を良くするのかを考えていきます。
勉強しなさいと言いたくないけどイライラする親心



勉強しなさいって言いたくない…でも、本当にしないとモヤモヤする。
現にそう感じる親は多いです。頭では「子どもの自主性を大事にしたい」と分かっていても、目の前でダラダラしている姿を見ると、ついイライラがつのりますよね。
「やらないと後で困るのに」「私ばっかり焦ってる…」と不安も膨らんできます。この不安は、親が子どもの未来を思っているからこその葛藤です。
子どもの行動に一喜一憂してしまうのは、「放っておけない気持ち」の表れです。不安や焦りがあること自体が、子どもをしっかり見ている証でもあります。
「ちゃんと見守りたいのに、なぜこんなに疲れてしまうんだろう」そう思った時は、まず自分の気持ちに気づくことが大切なステップになります。
「言わずに見守る」ことがただの我慢にならないように、「どう関わるか」の工夫が必要ですね。
言わなくても伝わるためには、どんな接し方ができるのでしょうか?次は、親の関わり方の工夫について考えていきましょう。
言わなくても伝わる関わり方の工夫3選
「勉強しなさいと言わない代わりに、どう関わるか」が大切です。下記のような工夫が、子どもの心に「伝わる関わり方」に繋がっていきます。


言わなくても伝わる関わり方の工夫
- 「やってないの?」ではなく「一緒に考えようか」
- 「毎日やること」ではなく「流れをつくる」
- 「見張る」のではなく「聴いている」
親の気持ちとしては自然なものですが、勉強しなさいと言わないことが「我慢」や「放置」になってしまうと、親も子も辛くなってしまいますね。
親も子も辛くならないよう、言わなくても伝わる関わり方の工夫、①~③を詳しくご説明します。
①「やってないの?」ではなく「一緒に考えようか」
子どもが勉強していない時、つい「どうしてやらないの?」と問い詰めたくなります。しかし、その言葉は子どもにとってプレッシャーになりがちです。
代わりに「どこでつまずいてる?」「いつやるのがやりやすいと思う?」と、寄り添う視点で声をかけてみましょう。
「勉強をする・しない」ではなく、「どうすればやりやすくなるか」を一緒に探って考えることが、子ども自身の気持ちを引き出すきっかけになりますね。



親が一方的に「いつ?」と聞いて決めさせるのではなく、一緒に考えて決めていくんですね。
長い時間がいい、短い時間がダメ、では全くありません。まずは、やりやすい時間帯を考えていくことが大事です。
②「毎日やること」ではなく「流れをつくる」
「毎日やる」と決めても、子どもが続かないことはよくあります。忘れてしまう、やりたくない、その日の気分が乗らない…理由はさまざまです。
そんな時は、「勉強する」という行動そのものを、生活の中に「組み込んでしまう」という発想も1つの手です。
たとえば、夕食後に5分だけ机に向かう時間を作ってみる。これを毎日続けると、「やる?やらない?」と迷うより先に、「やる時間が来たからやる」という流れができてきます。
歯をみがく、手を洗う、食事をする。そんな生活の一部として、少しずつ自然に習慣化していけると、親も子もストレスが減っていきます。



まずは①で決めた「子どもに合ったやりやすい時間帯」を、生活の中にさりげなく組み込んでみましょう。
③「見張る」のではなく「聴いている」
「ちゃんと見てるよ」と伝えたくて、つい子どもの様子を「見張る」ような態度になってしまうこと、ありますよね。
子どもは「見張られている」と感じるより、「聴いてもらえている」と感じた時に、安心して自分を出せるのです。
子どもが学校での出来事や困ったことを話してくれた時、すぐにアドバイスをするのではなく、まずは「そうなんだね」と、気持ちを受け止めてみましょう。
アドバイスは、子どもが本当に答えを求めている時で大丈夫。それまでは聞き役に徹し、子どもの話をじっくり聴いてあげてください。
親が何かをしながら聴くのではなく、子どもの方に体ごと向けて、子どもの話しに耳を傾けましょう。
無関心にならずに見守るバランス
「勉強しなさい」と言わないと、まるで無関心な親のように見えるのではないか…そんな不安を感じることもあるかもしれません。
実際に「うるさく言わない=放任」と思われるのが心配で、つい口を出してしまう親御さんも多いです。
本当に子どもに必要なのは「指示」よりも「信頼されて見守られている」感覚です。
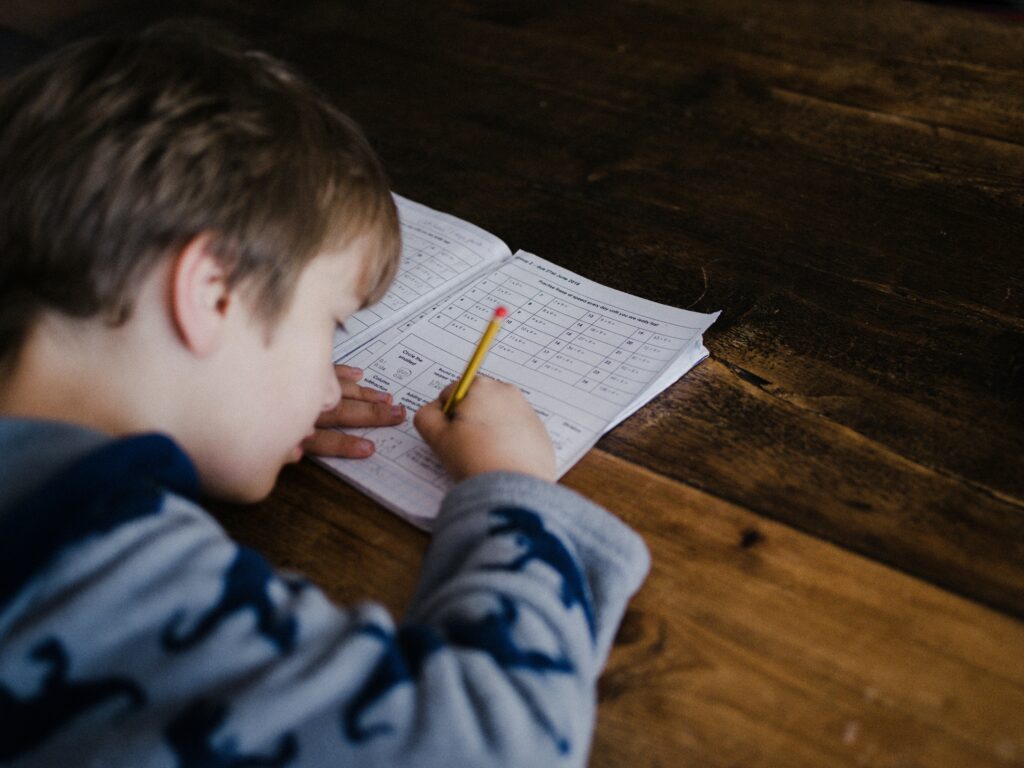
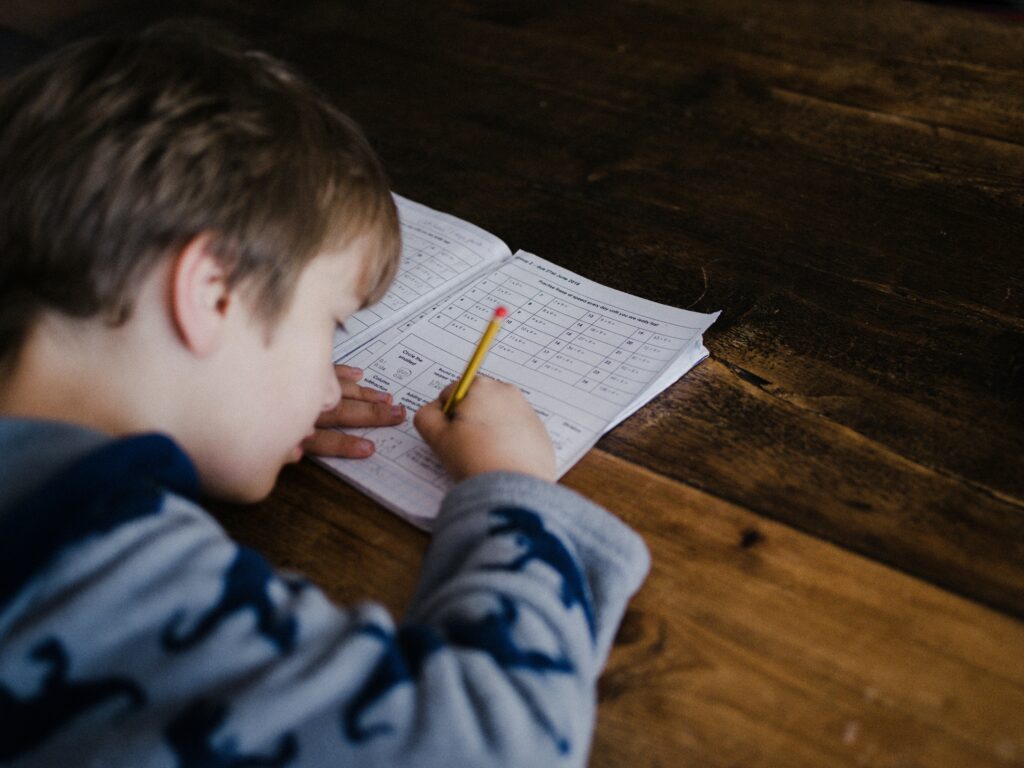
例えば、
- 宿題を終えた時に「頑張ってるね」と声をかける
- 自分から机に向かった姿を、そっと見守る
- 失敗しても「大丈夫」と支える姿勢でいる など
小さな関わりの中で、子どもは「見てくれてる」「応援してくれてる」と感じ、自分から動きやすくなります。
干渉しすぎず、でも無関心でもない。この中間の関わり方が、子どもにとっても親にとっても、無理のない距離感になるのです。



常に見張られているのは嫌だし、何も言われないのも寂しいから、これくらいの関わりがちょうどいいな。
\子どもとの対話がうまくいく秘けつが満載!/
勉強しなさいと言わない環境の整え方4選


子どもに勉強しなさいと言わないで、「やってみようかな」と思えるような空気や環境は、家庭の中で作ることができますよ。
- いつでも使える勉強スペースをつくる
- 子どもが自分で選べるようにする
- できたことに気づいたら伝える
- 家族の中に「学び」がある空気をつくる
大切なのは、「やらせる」ではなく、「自然とやる気が出る場」を整えることです。
「支えてくれている」と感じられる親子の関わりが、子どもの背中をやさしく押してくれますよ。
1つずつ、詳しく説明しましょう。
①いつでも使える勉強スペースをつくる
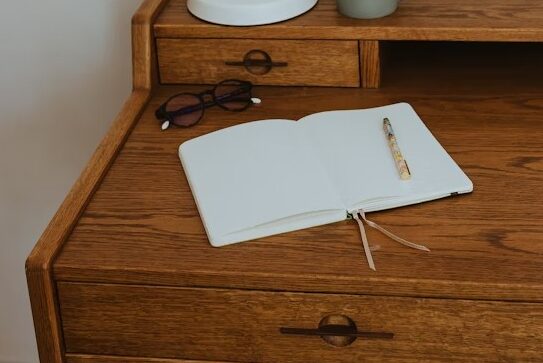
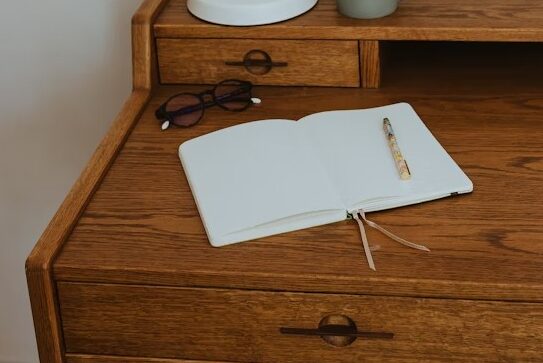
子どもが「よし、やろうかな」と思った時に、すぐに取りかかれる環境があると、それだけで勉強へのハードルがぐんと下がります。
ポイントは、「いつでも勉強してもいい場所」が家の中にあることです。親が「ここで勉強しなさい」と押しつける必要は全くありません。
「ここ、使ってもいいんだよ」「この場所、気に入ってるよね」とさりげなく伝えるだけでも、子どもの中には「自分の勉強場所」という意識が芽生えてきます。
「リビング学習」という言葉も耳にしますが、リビングでやるのが必ず良いのかと言えば、そうではありません。
家族のいるリビングの方が落ち着くという子もいれば、静かな個室が合う子もいて、実際は子どもによって集中しやすい場所はさまざまです。



場所が決まったら、親もその場所を大切に扱ってあげてくださいね。
「ここはあなたががんばる場所だもんね」と言葉をかけたり、机を一緒に拭いたり。子どもは「自分のことを応援してくれている」と感じとってくれますよ。
②子どもが自分で選べるようにする
「勉強しなさい」と言われてやる勉強は、どうしても「やらされている感」が付きまといますよね。
勉強しなさいと言わない中で、「どれからやろうかな」「このドリルやってみよう」と自分で選べると、子どものやる気は大きく変わってきます。


例えば、
- ドリルとタブレット、今日はどっちやる?
- 算数と国語、どっちからやる?
- この時間にやる?それともお風呂の後? など
選択肢を2つか3つにしぼって「選ばせる」ことで、子どもは自分の気持ちを言葉にしたり、考えたりする練習になります。
ここで大切なのは、親がコントロールしすぎないことです。
子どもが「今日はやらない」と言った時でも、「そっか、今日は休みたいんだね」と受け止めつつ、「また明日はどうするか一緒に考えよう」と次に繋がる声かけが理想的です。
親が「子どもが自分で決めたこと」を大切にしてくれると、子どもは勉強との距離をぐっと縮めてくれますよ。



大人もそうですが、決めたことをやりたくない日もありますね。子どもにだけ否定したり、反対したりするのは、良くないですね。
子どもがやらないと決めたら、反対せずに、まず受け入れる。次に繋げる声かけ、「また明日かどうしようか一緒に考えよう」ですね。
③できたことに気づいたら伝える
子どもが自分から何かに取り組んだ時、「できたね」と言われると、それだけで大きな喜びになります。
特に勉強に対して前向きになってほしい時には、「すごいね!」と大げさに褒めるよりも、小さな「できた」を見逃さず、具体的に伝えるのがポイントです。


例えば、
- 「昨日より早く机に向かえたね」
- 「この漢字、ていねいに書けてるね」
- 「自分で終わりの時間を決めて偉いね」 など
結果よりも、その子なりの工夫や頑張りに目を向けて伝えると、子どもは「自分はちゃんとできてるんだ」と気づけます。
それが自信に繋がり、「またやってみよう」という気持ちを育ててくれますよ。
また、子ども自身が気づいていない「できた」ことを言葉にしてあげられるのは、親だからこそできることです。
④家族の中に「学び」がある空気をつくる
「勉強しなさい」と言わないで、自然に子どもが学ぶ気持ちになるために大切なのは、家の中に「学び」が当たり前にある空気感です。


例えば、
- 大人が本を読んでいたり、調べ物をしていたり
- わからないことを「一緒に調べよう」と言ってくれたり
- 会話の中で「へぇ!それ面白いね」と知ることを楽しんでくれたり など
こんな日々の何気ないやりとりが、子どもにとっては「学ぶって楽しい」「分からないって悪いことじゃない」と思える土台になるのです。
子どもにだけ「やりなさい」と言うのではなく、大人も一緒に楽しんでいる。そんな空気があれば、子どもは無理なく、学びに向かう力を育んでいけそうですね。
\イラストやマンガで解説を加えた最新版!/
勉強しなさいと言わないでやる気・楽しさの育て方7選
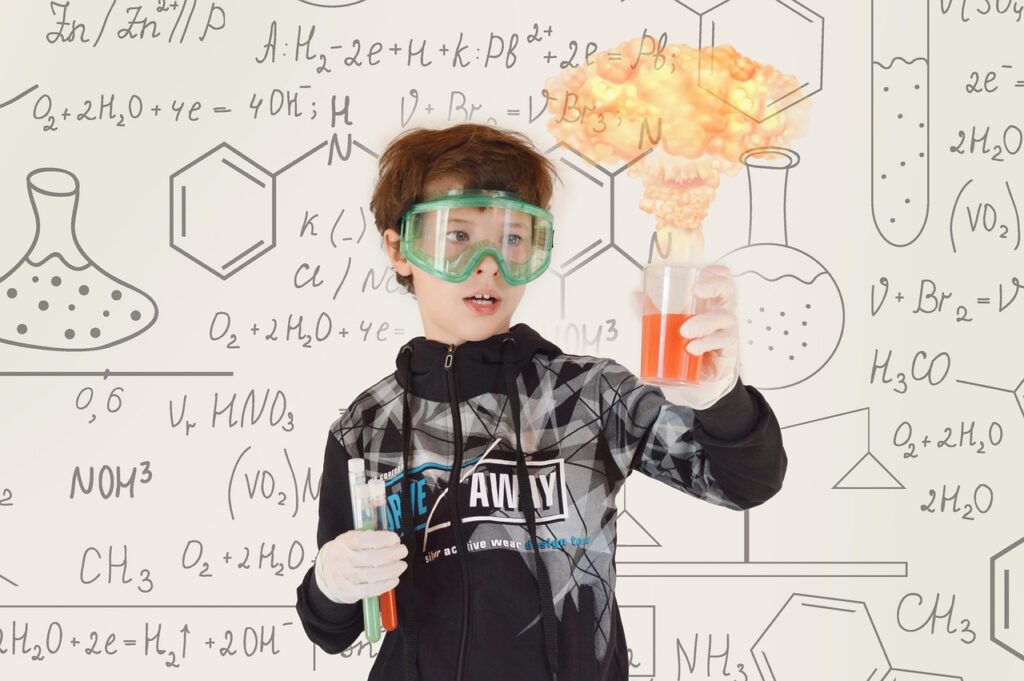
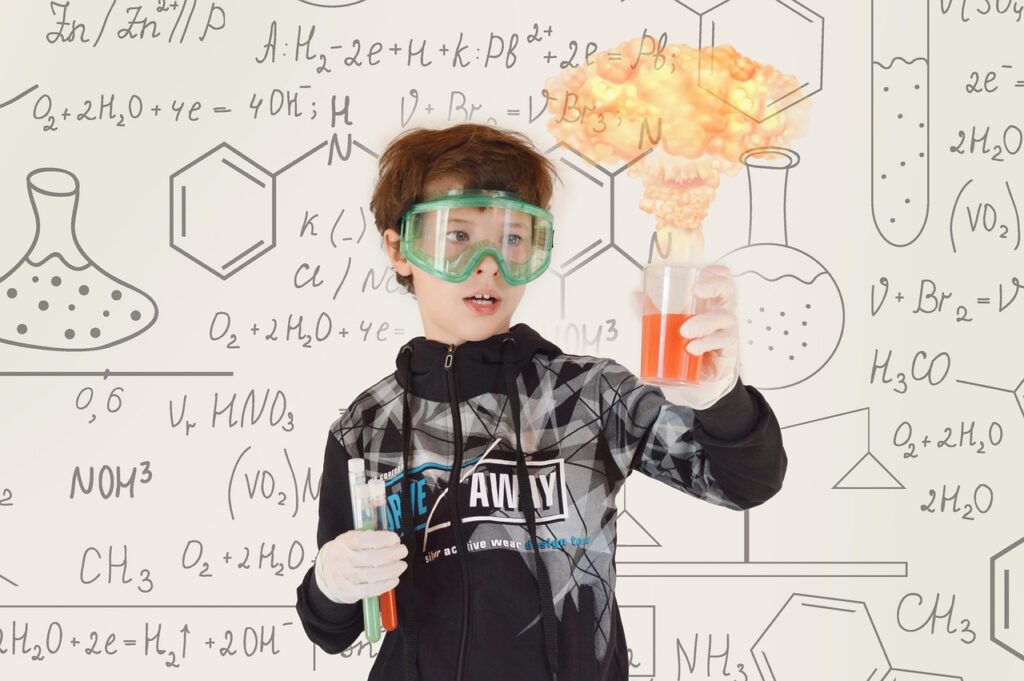
「勉強しなさい」と言わないで、自分から机に向かう子は、「やらされている」よりも「勉強が楽しいからやりたい」とやる気を感じている子が多いです。



勉強が楽しい?ひたすら知識を詰め込む授業は全然楽しくないし、何が楽しいか全然分からないよ。
子どもが「やってみたい」「もっと知りたい」と思う気持ちは、実はとても自然な心の動き。上手に引き出してあげれば、「勉強しなさい」と言わないのに、自ら学び始めるのです。
「勉強が楽しいからやりたい」というやる気は、特別な環境や教材でなくても、日々の関わりや声かけの中から育っていきますよ。
やる気は、強制的に勉強しなさいとさせられて生まれるものではない、と考えましょう。
- 子どもの「知りたい」を見逃さない
- 小さな成功体験を一緒に喜ぶ
- 興味のタネに気づく
- 話題をつなげる「学びの対話」
- 「知りたい」が深まったときのサポート
- 「おもしろかったね」で終わる体験を大切に
- 親が「勉強の話題」を前向きに語ってみる
ここでは、子どものやる気と、学ぶ楽しさを育てる関わり方について、具体的にご紹介します。
①子どもの「知りたい」を見逃さない



地球温暖化って、実際どれくらいヤバいの?
戦争って、なんでなくならないの?
子どもが興味をもったタイミングで、一緒に考えたり、図鑑やネットで調べたりすると、「知るって面白い!」という感覚が自然と育っていきます。
実は、子どもの何気ない質問こそが、「学びたい」という気持ちの「タネ」です。
子どものこの「タネ」を放っておくとそのまま枯れてしまいます。声をかけたり、一緒に調べたり、考えたりして関わると、興味が「芽」になり「学びの木」へと育つんですよ。
すぐに答えられなくても、「それ気になるね!一緒に調べてみようか」とまず返すだけで、子どもの心に学びの火が灯ります。後で調べるのを忘れずに!
家庭の中で「知りたい」という気持ちが受けとめられ、深められる経験を積み重ねていく。やがて「学ぶって楽しい」「もっと知りたい」と思える土台になるのです。
②小さな成功体験を一緒に喜ぶ
小さな行動や変化を見つけた時、親が「それすごいね!」「頑張ったんだね」と、心から一緒に喜ぶことが大切です。
子どもは、できたことを誰かに認めてもらうことで、「やってよかった」「次もやってみたい」という気持ちを育てていきます。



褒められたくて頑張るときもあるし、やっぱり褒めてくれると嬉しいから。喜んでくれたらもっと嬉しい!
親から見れば「ちょっとしたこと」に見えても、子ども自身が頑張ったら、それは立派な成功体験なのです。


例えば、
- 「お店の看板の漢字を読めた!」
- 「ゲームの攻略法を調べて、技を考えたんだよ!」
- 「お気に入りのキャラクターのグッズを手作りした!」 など
ポイントは、「結果」だけじゃなく「取り組んだことそのもの」を認めてあげることです。
学校の点数や順位よりも、「やったこと」「工夫したこと」に注目すると、子どもは「やればできる」「自分は成長できる」という自信を育てていけますよ。
親のたった一言のリアクションが、次の「やってみよう」を引き出す力になります!
「すごいね」「前より上手くなったね」「よく見てるね」といった言葉を、日々の小さな場面で惜しまず伝えていきたいですね。
③興味のタネに気づく
子どもがふと「なんで雲って動くの?」「地震ってなんでおきるの?」と聞いてきた時、すぐに答えを言うのではなく、「いい質問だね」「どう思う?」と一緒に考えてみましょう。
大人にとっては当たり前だったり、忙しくてスルーしがちな問いでも、子どもにとっては「初めて気づいた世界」なんですよね。



そんなの分からないよ!今忙しいから!と言わないで、分からないならなおさら、子どもと一緒に考えていけますね。
一緒に調べて、専門用語があれば分かりやすく子どもに説明すると、親の説明力も一緒に鍛えられそうですよ!
子どもは「自分の疑問を大事にしてもらえた」という実感になり、次の「知りたい」に繋がっていきます。
④話題をつなげる「学びの対話」
テレビで出てきた言葉、ニュースで見かけた出来事、ゲームやアニメの話題にも、ちょっとした「学びのタネ」が隠れています。
例えば「このキャラクターの名前、昔の歴史上の人物からきてるんだよ」「このゲームのマップ、日本と似てるね」など、日常と学びが繋がるような会話をしてみましょう。



歴史上の人物だったんだ!このキャラ好きだったから、ちょっと調べてみようかな。
「勉強は教科書を覚えるだけじゃない」と感じてくれると、「難しい=勉強」のイメージが少しずつ変わっていけそうですね。



私も一緒に調べてみたい!
どんなアニメを観ているのか親が分かっていないと、話せない会話ですね。何を熱心に観ているのか子どもに聞いたり、一緒に観たりして分かることです。
子どもに関心を持って、「教えて!」「テレビで一緒に観ようよ!」と関わると、子どもは放っておかれないし、寂しい思いをせずに済みますね。
⑤「知りたい」が深まったときのサポート
もし子どもが何かに夢中になっている様子があれば、そのタイミングを逃さずに図鑑を開いたり、関連するYouTube動画を一緒に見たり、本屋で関連書を探してみるのもおすすめです。
子どもが「もっと知りたい」と感じた瞬間に、そっと背中を押す存在でいられると、学びの好循環が生まれます。



もっと調べたいから、図書館か本屋さんに行きたいから連れてって!ママも一緒に調べてね!



もちろんいいよ!一緒に行こうか!
⑥「おもしろかったね」で終わる体験を大切に
アニメでも漫画でもゲームでも、「面白い!楽しい!」と、感じやすいですよね。逆に学校の授業は「つまらない」と感じがちです。
この違いは、「自分から夢中になれたかどうか」にあります。
子どもが「面白かった!」と思える体験には、興味や関心、自分なりの発見があります。「自分で見つけて、自分で楽しんだ」という感覚があるんですね。
勉強も同じ。最初はつまらなく見えても、自分で発見したり、ちょっとした疑問を調べて「わかった!」と感じられる瞬間が、自然と「面白いかも」に変わっていきます。
「これってどういう意味?」と一緒に調べてみたり、漢字の成り立ちを一緒に考えたり。「学び」が「面白かったね」で終わる体験に変わっていきます。



息子は漢字の宿題だけはやる気で、漢字辞典からゲーム感覚でことわざや故事成語の問題を私に出したりします。



私は全然分かんないけど、クイズの時間はママとお兄ちゃんが楽しそうだから好き!
そうした体験の積み重ねが、子どもの中に「学ぶって悪くないかも」という気持ちを育ててくれるのです。
⑦親が「勉強の話題」を前向きに語ってみる
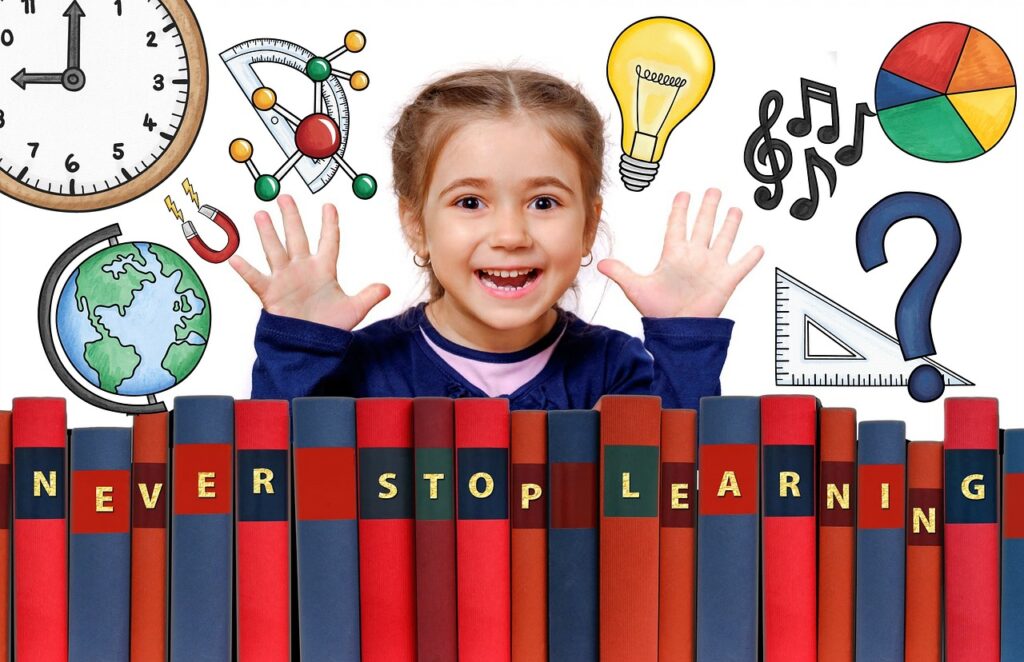
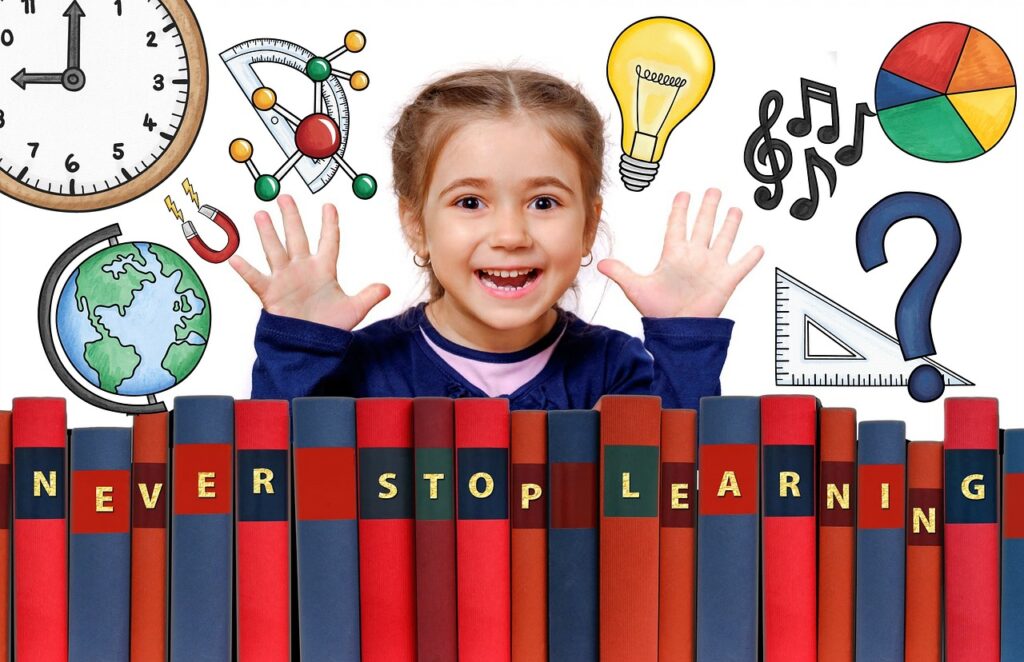
親が「知ることを楽しんでいる」様子を見せると、子どもが勉強を前向きに捉える大きなきっかけになります。
子どもは、親がどんなことを「楽しい」と感じているか、とても敏感に感じ取っているのです。
親自身が「知るって面白いな」「やってみたら意外と分かってきた」といった感覚を、日常の中で少しずつ言葉にしていきましょう。
つい「私も勉強嫌いだったよ」「やらなきゃいけないからね」なんて言ってしまうこと、ありますよね。
そんな一言も、子どもにとっては「やっぱり勉強ってつまらないものなんだ」と思わせてしまうのです。
「この前〇〇のこと気になって、自分で調べちゃったよ」「昔、算数のこの単元は好きだったな」など、前向きなエピソードを話してみたり。
料理中に「レシピに、理科と算数で習った単位があるよ」とか、一緒に出かけた時に「この道って、どこまで続いているのかな」と言ってみるだけでもOK。



この前の授業で、星の名前がたくさん出てきたよ。アンタレスとかアークトュルスとか、名前がカッコいいって思った!



理科で星を習っているんだね。星はギリシャ神話の神様の名前が由来なんだよ。ギリシャ神話を読んだら面白かったな。
勉強に前向きな空気が、家庭の中に少しずつ広がっていきますね。
\子どもはゲーム大好き!なら学びに変えちゃう⁉/
まとめ
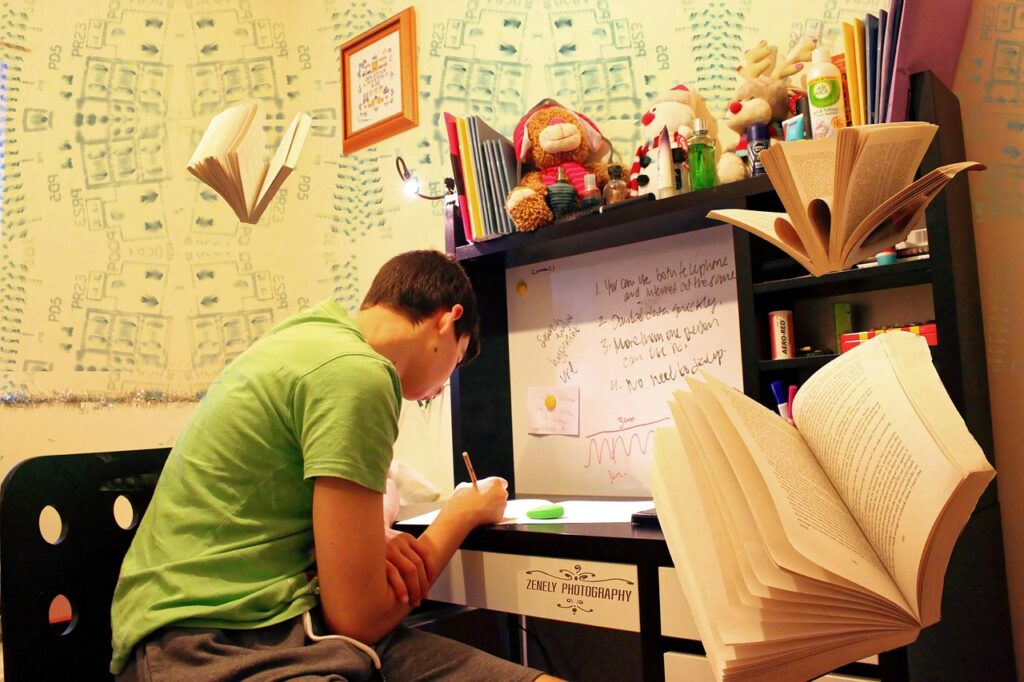
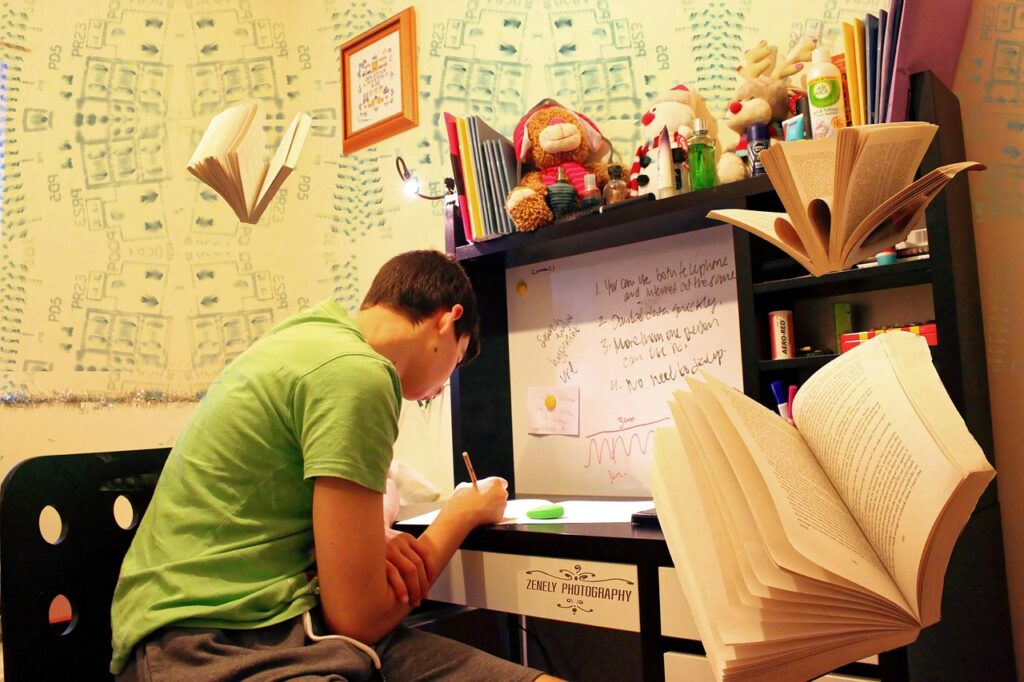
- 私が帰宅するとランドセルは放り出されたままで子どもたちはゲームに夢中、宿題は毎日あるのにランドセルを開けた形跡すらない現実がある
- 子どもは脳の未発達のために「今やるべきこと(宿題)」と「今やりたい楽しいこと(ゲーム)」を比べて今やりたいことを優先する
- 親は勉強しなさいと言わない気持ちと、本当にしない焦りとイライラで葛藤を抱えている
- 言わなくても伝わる関わり方の工夫3つ①やりやすい時間を一緒に考える②生活に組み込んで流れをつくる③子どもの話しを聴く
- 勉強しなさいと言わないで勉強するようになる環境は、「やらせる」ではなく「自然とやる気が出る場」を整える
- 子どもを主として一緒に場所やドリルを選び、親はコントロールしすぎないことが大切
- 子どもが「やってみたい」「もっと知りたい」と思う気持ちは自然な心の動きで、上手に引き出すと、勉強しなさいと言わないままでも自ら学び始める
- 親が「知ることを楽しんでいる」様子を見せれば、子どもが勉強を前向きに捉える大きなきっかけになる
「勉強しなさい」と言わない。しかし、本当にしない子どもを見ると、つい言いたくなってしまう…そんな葛藤を抱える親は多いです。
子どもが今やりたいことを優先する理由は、脳の発達途中でもあり、「将来のために今がんばる」という思考はまだ育ちにくいからです。
ただ勉強をやりたくないから本当にしない、とは違うのです。だからこそ、親がその力を支える関わり方を意識するのが大切なのですね。
「いつならやりやすいかな」「どこでやりたい?」と一緒に考える姿勢や、「疑問を一緒に調べる」体験が、子どもにとって「知る楽しさ」を感じるきっかけになります。
息子と話し合いの結果、選んだ勉強場所はリビングに、まずは夕食の準備中に宿題をすることになりました。
「僕、本当はね、妹がママの近くで宿題をするのが羨ましかった…。」私は、見守るどころか寂しい思いをさせていたことに反省し、今後は関わりをもっと増やそうと思いました。
「やらせる」ではなく「やりたくなる」環境を、日々の中で少しずつ整えていく。焦らなくて大丈夫です。
小さなやる気の芽を、親子で一緒に育てていきましょう。


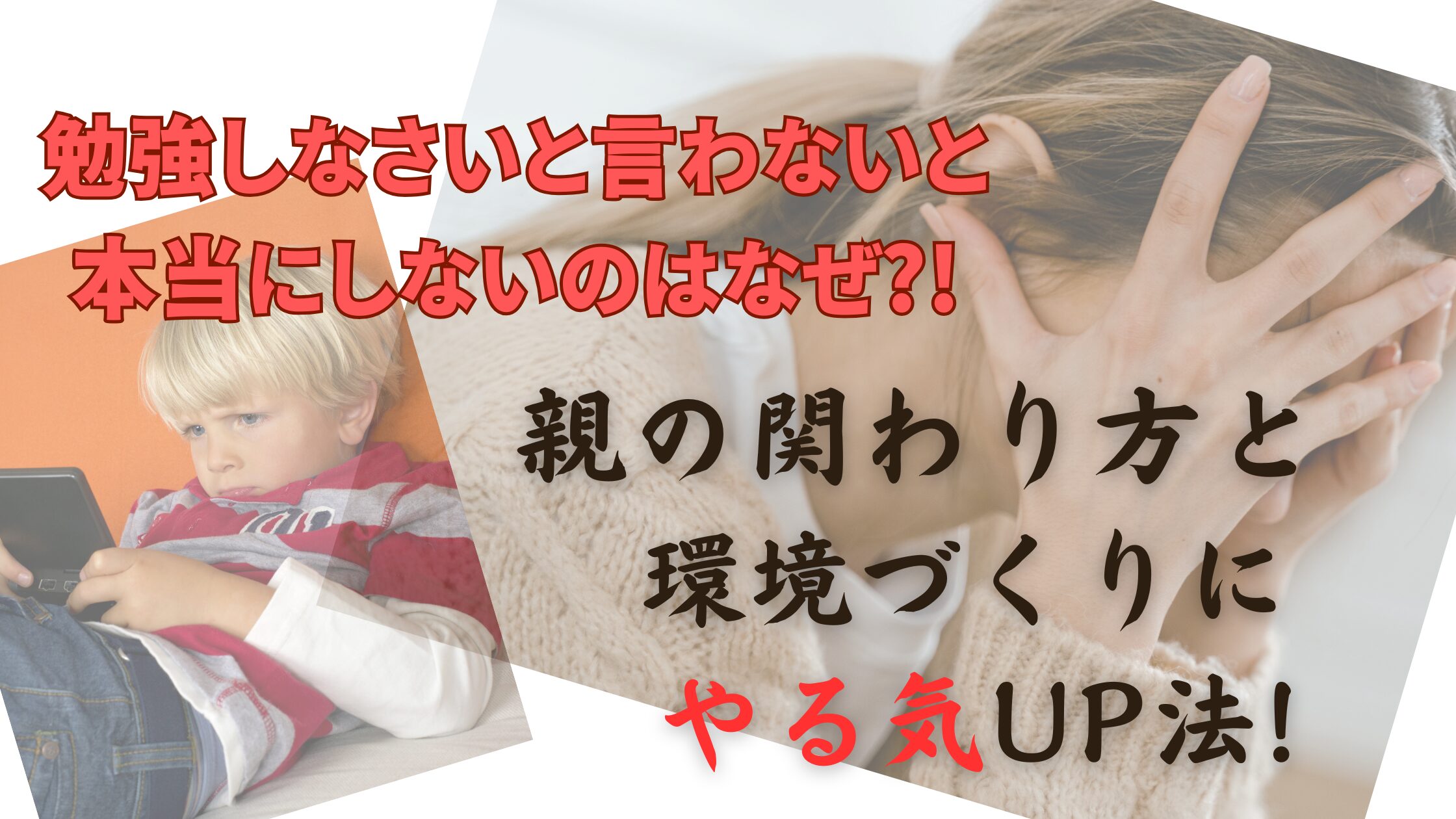








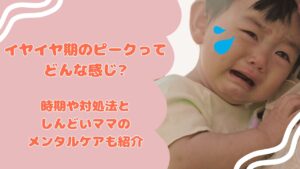
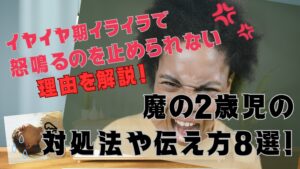

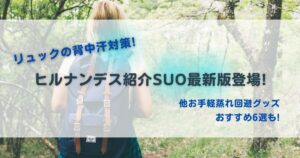
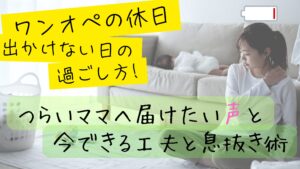

コメント