 友人
友人つかまり立ちし始めたからベビーベッドを下段にしたんだけど、寝かせるのが難しくなったんだよ。
先日6ヵ月の赤ちゃんがいる友人がこのように話していました。
今まで赤ちゃんを抱っこで寝かせていた友人は、ベビーベッドに降ろす際どうしても赤ちゃんが起きてしまい、寝かせ方に悩んでいたのです。
調べてみたところ、ベビーベッドの下段の寝かせ方には3種類あり、その中でもねんトレを活用した方法は身体への負担を減らせ、おすすめであることがわかりました。
今回は、ベビーベッドを下段にすることにより悩みが増えたママに、腰の痛みを軽減するための方法やベビーベッドを卒業した後の寝方のアイディアもご紹介します。



寝かせ方の悩み、身体の不調を解消して子育てライフを楽しみましょう♪
\21種の癒しの音で赤ちゃんも安心して眠れる!寝かしつけの際の生活音対策にもおすすめ/
ベビーベッドの下段の寝かせ方





下段の寝かせ方、他にどんなものがあるんだろう?
つかまり立ちを始める生後6ヶ月前後で下段にし、それ以降もベビーベッドを使用していた場合の寝かせ方には3種類あります。
- 抱っこで寝かせてからベビーベッドに移す
- 大人のベッドで添い寝して寝かせた後ベビーベッドに移す
- 始めからベビーベッドに寝かせる
それぞれ詳しい方法をご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
1.抱っこで寝かせてからベビーベッドに移す
抱っこで寝かせてからベビーベッドに移す方法で寝かせていたのに、下段になった途端降ろすのが大変で悩むことが多いと思います。
抱っこで寝かせることを成功させるポイントは以下の通りです。
- 抱っこしながら部屋を歩きまわり寝かせる
- ベッドに降ろすタイミングは寝た後8分待ってから
私は2人の子どもを育てる母なのですが、1人目のお昼寝のときに実践していた寝かせ方です。
我が家は布団を囲わずに添い寝していましたが、1歳を過ぎる頃から布団から脱走してしまい寝かせることが難しかったため、確実に寝てくれる上記の方法をとっていました。
抱っこしながら部屋を歩きまわり寝かせる
抱っこの時間が長くて辛いママへ、最短で寝かせる秘訣は抱っこしながら部屋を歩き回ることです。
やり方は、赤ちゃんとしっかりと密着するように抱っこし、通常の歩く速さで良いので家の中をひたすら歩き回ります。
このように抱っこしながら歩くことで、赤ちゃんがリラックスすることが研究で分かっています。
母親が歩いている時は、座っている時に比べて赤ちゃんの泣く量が約10分の1に、自発的な動きが約5分の1に、心拍数が歩き始めて約3秒程度で顕著に低下することを見いだし、
赤ちゃんがリラックスすることを科学的に証明しました。
引用元 理化学研究所
これは”輸送反応”というもので、猫やライオンなどの 哺乳類の子どもは外敵から逃れる際親にくわえられながら移動するのですが、子どもが暴れて落ちないように備わった反応です。
人間の赤ちゃんにもこの反応が備わっているんです!
リラックス状態になることで寝つきもよくなりますので、抱っこしながら歩くことは効果的です。
ベッドに降ろすタイミングは寝た後8分待ってから



せっかく寝たと思ってベッドに降ろしたら起きてしまった
これは背中スイッチといって、まるで背中にスイッチがあるかのようにベッドに降ろすと起きてしまう現象のことです。
精神的にも肉体的にもママへのダメージは大きいですよね。
そうならないためのポイントは、赤ちゃんが寝たと思ったらそこから更に8分待ってからベッドに降ろすことです。
理化学研究所が発表した研究結果によると
赤ちゃんをベッドに置いて起きてしまった例では、眠った後、平均3分間座って抱っこした上でベッドに移していた。起きなかった例では同8分だった。
睡眠開始から約8分経つと眠りの浅い段階を過ぎるため、深く眠りやすくなるとみられる。
引用元 理化学研究所



寝た後8分待つ間は、椅子などに座っても大丈夫です
せっかちな私は、寝たと思ったらすぐベッドに降ろしてしまい赤ちゃんが目を覚まし、もう一度抱っこということが何度もありました。
2.大人のベッドで添い寝して寝かせた後ベビーベッドに移す
ベビーベッドで寝てくれないけれど、睡眠中の安全を確保するためどうしてもベビーベッドで寝かせたいというママにおすすめの方法です。
- 抱っこするタイミングがベビーベッドへ移動するときだけなので身体への負担も減らせる
- 添い寝することで赤ちゃんがリラックスでき寝つきやすくなる
ベビーベッドへ移動する際に起きてしまうのを防ぐため、抱っこでの寝かしつけ方でも紹介した寝た後8分待ってからを活用しましょう。
添い寝であれば待つ時間も楽ですし、しっかり深い眠りに入ってくれてるので背中スイッチで起きる頻度が格段に減らせます。
3.初めからベビーベッドに寝かせる
こちらは、寝る前の授乳などを終えた後、ベビーベッドに赤ちゃんを横たわらせ自分で寝てくれるのを待つ方法です。
この方法を成功させるために最もおすすめなのが“ねんトレ”です。
ねんトレとはねんねトレーニングの略で、赤ちゃんが抱っこや添い乳をしなくても朝までぐっすり眠れるようにトレーニングをすることです。
下段に変更する生後6ヵ月頃は体重6㎏~9kgと重く、身体への負担も大きくなってくるかと思いますので、抱っこでの寝かし付けが難しくなったらねんトレを始めるチャンスです。
ベビーベッドは、赤ちゃんにとって危険な物を置かないようにすれば目を離しても安全なため、ねんトレにもってこいです!
ベビーベッドの下段はねんトレに最適!


先ほどお伝えしたように、活発に動きだした赤ちゃんにとってベビーベッドの下段は安全を確保しやすいため、安心してねんトレを始められる最適な場所といえます。



下段にしたしねんトレを始めてみようかな
赤ちゃんの寝床をベビーベッドの下段にしようと考えているあなたに、ねんトレがスムーズ進むための下準備とやり方をご紹介していきます。
ねんトレの下準備
ねんトレは、いきなり初めてもうまくいきません。
しっかりと下準備をしてから行うことが成功の近道になります!
ねんトレの下準備はこちらです。
- ねんトレを始める日を決める
- ねんトレを始めることを赤ちゃんに予告する
- 寝る環境を整える
- 日中の活動限界時間を知り昼寝を適宜する
- 寝る前のルーティンを決める
- 家庭内で共有する
②~⑤はねんトレ以外でも寝つきをよくするために活用できますので、参考になさってください。
それではひとつずつ詳しく見ていきましょう♪
①ねんトレを始める日を決める
ねんトレを始める日は、前後1週間で予定がなく赤ちゃんの体調の良いときにしましょう。
体調の悪い時は、普段よりもママにくっつき安心したい子が多いので離れることが難しく、ねんトレがスムーズに進みにくくなってしまうためなるべく避けましょう。
外泊する旅行や1日しっかり予定が入っている日はいつもとスケジュールがかわってきてしまいます。
②ねんトレを始めることを赤ちゃんに予告する
ねんトレを始める日を決めたら、1週間ほど前から「○日からひとりで寝るんだよ」と赤ちゃんに予告します。
お話がまだできない赤ちゃんですが、言葉をよく聞いて理解もしています。



泣いてもいつかは寝るらしいしもう疲れたから抱っこするのやめよう
このように、いきなり衝動的にねんトレを始めるのは失敗のもとです!
今まで抱っこや授乳で寝かせてくれていたのに、急に突き放され不安になり泣き続けるといった状態になってしまいます。



衝動的に始めると、その後の罪悪感もありママもストレスになってしまうので計画的に始めましょう!
事前に伝えておくことで、赤ちゃんもママも心の準備ができるのでおすすめです。
③寝る環境を整える
次に赤ちゃんが寝つきやすくするためのポイントは、寝る環境を整えることです。
| ①音、映像 | テレビやスマホは夕方まで |
| ②光 | 寝る際、部屋は常夜灯も消し真っ暗に |
| ③温度 | 夏は25度~27度、冬は18度~20度が目安 |
明りを暗くする際、赤ちゃんに「寝る時間だから電気を消すね」といいながら消します。こうすることで赤ちゃんは寝る時間なんだと認識することができます。
温度を適温にするのは難しいご家庭もあるかもしれませんが、衣類で調整したり、エアコンの場合は直接風が当たらないようにしたりと配慮しましょう。
④日中の活動限界時間を知り昼寝を適宜する
活動限界時間とは、赤ちゃんや子どもが元気に活動できる限界の時間のことです。
この時間を超えて起きていると疲労が溜まり眠いのに上手く寝ることができず、泣き続けたり不機嫌になってしまったりします。
活動限界時間を意識し、適宜昼寝をすることで寝付けずに泣く寝グズリが起こりにくくなり、寝かしつけもスムーズになります。
- 1~2ヶ月: 40分~1時間
- 2~5ヶ月: 1時間~1時間20分
- 6ヶ月~10ヶ月: 2時間~3時間
- 11ヶ月~12カ月: 3時間30分~4時間
- 1歳~1歳半: 4時間~6時間
あくびは眠くなった合図ではなく、活動限界が近いか限界を超えている合図であるため、あくびをし始める前に寝かし付けを始めましょう。
⑤寝る前のルーティンを決める
これが終わったら寝る時間なんだと赤ちゃんに理解してもらうために、夜のルーティンを決めて毎日同じことを繰り返すことが重要になってきます。
例としては、
- お風呂
- 保湿
- 授乳(卒乳していれば水か麦茶で水分補給)
- 歯磨き
- 毎日同じ絵本を読む
- 暗い寝室に行く
- おやすみと伝える
- 寝床に寝かせる
ご家庭により内容が変わったり前後したりするかと思いますが、ポイントは毎日同じ時間にルーティンをスタートし毎日同じ順番にやることです。
⑥家庭内で共有する
ねんトレは、初めのうちは泣いている赤ちゃんの様子をみながら待つ時間があります。
自分で寝る習慣を身につけてもらう必要があるため、まったく泣かないというは難しいものです。
パパや一緒に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんがいる場合は、全員に情報を共有しておくとスムーズです。
また、寝かしつけの悩みはママだけで抱え込まず、どんなねんトレ法でやっていくか決める段階からパパと話し合い協力してもらうようにしましょう。
ねんトレのやり方
ねんトレの下準備が整ったら、いよいよ実際にねんトレをしていきます。
ねんトレのやり方は一つではなく、さまざまな方法があります。
赤ちゃんが寝る部屋の外で見守るやり方と、初めのうちは一緒に部屋の中にいて徐々に距離をとっていくやり方をご紹介します。



ご家族で相談して合うやり方を試してみてください♪
赤ちゃんが寝る部屋の外で見守るやり方
赤ちゃんが寝る部屋の外で見守る方法は、部屋に赤ちゃんを残していかなければならないですが、慣れれば最短でねんトレを完了できます。
詳しいやり方はこちらです。
- 寝るまでのルーティンを決めて毎日同じことをする
- ベビーベッドの下段に寝かせ、「おやすみ」などと声をかけ寝室を出る
- 泣き止まないようなら3分待った後、寝室に入り「ママいるよ」と1分程声をかけ寝室を出る
- 泣き止まないようなら5分待った後、寝室に入り「ママいるよ」と声をかけ寝室を出る
- 徐々に様子を見る時間を長くしていきながら泣き止むまで繰り返す
泣き声を聞きながら待っている時間はとても長く感じるかと思いますが、多くの赤ちゃんは40分前後で泣き止み自分で寝ることができます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 赤ちゃんが寝室で一人になることで他の刺激がなく寝ることに集中でき、最短でねんトレが完了する 部屋の外で待つ時間に家事や他のことができる | 赤ちゃんを部屋に一人にしないといけないので、抵抗がある場合はハードルが高い |
初めのうちは外で待つ時間も短いですが徐々に長くなっていくため、普段なら寝かし付けを完了してからやっていた家事などを合間ですることができます。
赤ちゃんを部屋に一人にするなんて耐えられない!というあなたへ、時間はかかりますが同じ部屋にいるところからスタートするやり方をご紹介します。
初めのうちは一緒に部屋の中にいて徐々に距離をとっていくやり方
初めから部屋の外で待つやり方よりも時間はかかりますが、最初のうちは近くで見守ることができるので、赤ちゃんを一人にすることに抵抗があるママにおすすめです。
詳しいやり方はこちらです。
- 寝るまでのルーティンを決めて毎日同じことをする
- ベビーベッドの下段に寝かせ、「おやすみ」などと声をかけベッドの隣に座る
- 激しく泣くようなら「ママいるよ」などと声をかけるかトントンする
- 完全に寝付いたことを確認したら寝室を出る
ベビーベッドとの距離を毎日少しずつ離していくと同時に、4日目以降は激しく泣くとき以外はトントンせず声掛けのみ、7日目以降は声掛けのみしてきます。
10日目くらいから部屋の外で見守り、2週間程でねんトレが完了します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 数日間は赤ちゃんと同じ部屋にいるので、様子がわかり安心 | 寝ることに集中しずらいため寝付くまで時間がかかる 暗闇の中、隣で赤ちゃんの泣き声をずっと聞いていないといけないため辛い |
ママがいることが気になり、つかまり立ちをする赤ちゃんであればこちらに手を伸ばしてくるかと思いますが、できるだけ反応せず見守りましょう。
暗闇の中、泣き声をひたすら聞く時間は想像以上に辛いものです。



旅行行くならここに行ってあれもしたいな、明日のご飯何にしようかななど考え事のテーマを決めて妄想に徹すると乗り切れます!
また、上記の方法をやってみたけれど泣き声を隣でずっと聞いているのがあまりにも辛いという場合は、部屋を出るやり方へ変更しても大丈夫です。
ねんトレを成功させるコツ
ねんトレを成功させるコツは以下の通りです。
- 行動に一貫性をもたせ絶対やるんだという強い意志を持つ
- 上手くいかなかったら、ねんトレの下準備ができているのかもう一度確認する
途中で抱っこしたり授乳して寝かせてしまうと赤ちゃんが混乱してしまったり、これだけ泣けば寝かせてくれるんだと学習してしまいます。
途中で抱っこしたり授乳したりしないねんトレのやり方でやっていくと決めたら、ねんトレが完了するまで貫き通しましょう。
また、どうしてもねんトレがうまく進んでいかないようであれば、下準備がきちんとできていて寝つきやすい状態になっているのかもう一度立ち返り確認しましょう。



一人ねんねができるようになると夜間の頻回授乳も減らしていくことができるので、ママの安眠にもつながります
寝かしつけに困っているようでしたらぜひ挑戦してみてください!
ベビーベッドの下段で腰の痛みに悩む人のための対策


産後の骨盤のゆがみと日々の抱っこやおんぶによる腰の痛みに加え、ベビーベッドを下段にしたことで前傾姿勢にならないとベッドに降ろせないため痛みが増してしまいます。
とはいえ、ベビーベッドをせっかく購入したし、赤ちゃんを安全に寝かせることができるなら少しでも長く使いたいと思うママも多いですよね。
正しい抱っこの方法やストレッチを実践すると、腰の痛みを和らげることができます。



腰の痛みは辛いですよね。一緒に改善していきましょう!
正しい抱っこの仕方
正しい抱っこをすることで、ベビーベッドの下段の際だけでなく、普段抱き上げたり降ろしたりするときにも負担がないです。



抱っこの姿勢を見直すだけで、腰への負担を大幅に減らせますよ
- 足を肩幅に開き膝を軽く曲げる
- 身体全体を使う意識で持ち上げる
- 抱っこ中はできるだけ密着する
ベビーベッドの下段から赤ちゃんを抱き上げる際、直立した状態から前かがみになると腰への負担が大きいため、足を肩幅に開き、膝を軽く曲げ身体全体を使う意識で持ち上げましょう。
降ろす際も同様で、直立にならないようにし、足を肩幅に開き膝をなるべく曲げるようにします。



抱っこの際はこちらを意識してみてください
腰の痛みを和らげるストレッチ
妊娠中は大きなお腹を支えるため、産後は赤ちゃんを抱っこする姿勢から反り腰の状態が続いてしまいます。
反り腰は、上半身と下半身をつなぐ腸腰筋(ちょうようきん)を衰えさせ、さらに骨盤が正しい位置に戻りにくくなってしまいます。
そのため腸腰筋を鍛えることで反り腰の改善が期待でき、骨盤が正しい位置に戻ることで腰痛も改善します。
こちらの動画は、美筋ヨガトレーナーの廣田なおさんが、5分でできる腸腰筋のストレッチを紹介しています。
腰痛と坐骨神経痛に悩んでいた私ですが、こちらのストレッチを続けることでどちらも改善しました。



腸腰筋を鍛えることは、産後の気になるぽっこりお腹にも効果がありますよ
5分でできるストレッチですので、家事の合間や寝る前の習慣に取り入れてみてください。
ベビーベッドの下段のその後の寝方3選!


ベビーベッドの寝かせ方や腰痛対策をご紹介してきましたが、やっぱり下段は使いにくいというママや、赤ちゃんが大きくなり窮屈そうだから卒業を考えたいと思うママもいらっしゃいますよね。
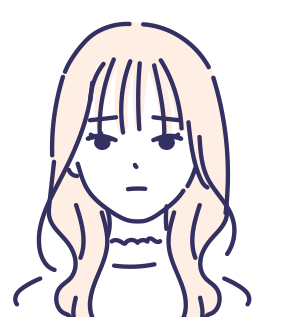
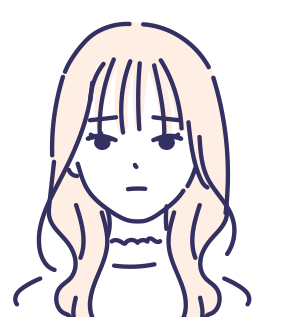
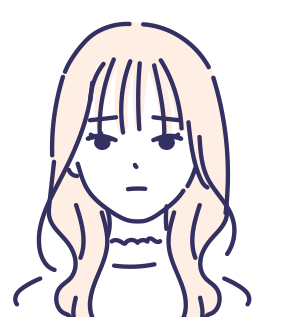
ベビーベッドのその後の寝方どうしようかな?
そうお悩みのあなたに、ベビーベッドのその後の寝方のアイディアをご紹介します。
- 布団をベビーサークルで囲む
- ベッドをベビーガードで囲む
- サークルやガードを使わず布団かベッドで添い寝
安全が確保しやすいベビーベッドを卒業するとなると、安全面が一番気になるところですね。
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
布団をベビーサークルで囲む
こちらは、布団かマットレスを敷きその周りをベビーサークルで囲む方法です。
ベビーベッドの下段のように抜け出すことが難しいため、寝ている間安全が確保されやすくお勧めの方法です。
こちらはベビー布団のサイズに合うベビーサークルで周りを囲ったアイディアです。
ベビーサークルの大きさを大人の布団が入るサイズのものにすれば、赤ちゃんと添い寝することもでき、添い寝したいママにもおすすめです!
\成長に合わせて組み換えも自由自在!吸盤付きで倒れる心配もなし!/
ベッドをベビーガードで囲む


こちらは、ベッドに専用のガードをつけ赤ちゃんの落下を防ぐ方法です。
寝がえりや寝ぼけて歩き出してベッドから落ちることを防げるためママやパパも安心して眠ることができます。
しかし注意したいポイントは、ベビーガードは1歳半以降でないと使用できないことです。
生後6ヵ月や生後9ヵ月の赤ちゃんが、ベッドガードとマットレスの間の隙間に落ちて亡くなるという悲しい事故が起きてしまったため、1歳半未満の使用が禁止されています!
また、1歳半以降でもベビーガードに挟まれた際、自力で抜け出せるだけの力がまだない可能性もあります。
ベビーガードは、安全性に配慮されたSGマークの商品を選ぶか、マットレスとガードの間に隙間ができない構造のものを選ぶと安心です。
\ベッドガードとマットレスの間に隙間ができない構造で安心!高密度スポンジ素材で寝がえりでぶつかっても痛くない♪/
サークルやガードを使わず布団かベッドで添い寝
こちらは、布団かベッドの配置を工夫して川の字で寝る方法です。
添い寝で赤ちゃんも安心して眠れますし、場合によっては布団やベッドを買い足す必要がありますが成長してからも使えるため長い目でみても無駄がありません。
ベッドは、壁にぴったりとくっつけ壁側に赤ちゃん、その隣にママかパパが寝ます。
そうすることで両サイドからの落下は防げます。
私の息子も、2歳頃にベッドの足元から落下し夜中に大泣きしました。
両サイドは壁と私で挟まれていたので安心していましたが、まさか足元から落ちると思っていませんでした。
また、布団やベッドから抜け出し歩き回る可能性もあるので、赤ちゃんが口に入れると危険なものは寝室に置かないようにしましょう。
まとめ


- ベビーベッドの下段の寝かせ方は3種類あり、①抱っこで寝かせてからベビーベッドに移す②大人のベッドで添い寝して寝かせた後ベビーベッドに移す③初めからベビーベッドに寝かせる
- 抱っこしながら部屋を歩き回り寝かせることで早く寝かせることができ、寝た後8分待ってからベビーベッドに降ろすことで寝かしつけの成功率が上がる
- 大人のベッドで添い寝してからベビーベッドへ移すため赤ちゃんも安心して眠れ、抱っこはベビーベッドへ移すときだけなので身体への負担も少なくて済む
- 初めからベビーベッドで寝かせる方法としてねんトレがあり、身体への負担も少ないため、寝かせ方の中で最もおすすめ
- ねんトレは、計画的に行うことが成功の近道であるため、1週間前から赤ちゃんに伝えておく、寝る環境を整えるなどの下準備をしっかりしてから始める
- ねんトレのやり方は赤ちゃんが部屋で一人で寝る方法と初めのうちは隣に座り徐々に離れて最終的に一人で寝れるようにしていく方法がある
- 正しい抱っこの仕方は足を肩幅に開き、膝を軽く曲げ身体全体を使う意識で持ち上げる。産後衰えがちな腸腰筋のストレッチをすることで腰痛が改善できる
- ベビーベッドの下段を卒業した後の寝方は3種類あり、①布団をベビーサークルで囲む②ベッドをベビーガードで囲む③サークルやガードを使わず布団かベッドで添い寝する
ベビーベッドを下段にすることで、なかなか寝てくれなかったりベッドへ降ろす際、腰が痛かったりと使いにくさを感じている方も多いかと思います。
ベビーベッドは四方がしっかりと囲まれており、赤ちゃんにとって一番安全な場所といえます。
お家にあるベビーベッドを使用期間いっぱいまで使い倒すことができるよういろいろな方法をご紹介しました。
その中で私がおすすめなのはねんトレです。
私自身も、娘の卒乳の際今まで授乳でしか寝られないと思っていた娘が、5日もしたら一人で寝られるようになり驚いたことがありました。
親の助けがなければ寝られないと思い込んでいましたが、寝方を知らないだけで、どんなに小さな赤ちゃんでも一人で寝られる力を持っています。
とはいえどうしてもベビーベッドが使いにくい、一人で寝かせるなんて無理という場合は、ベビーベッドを卒業したり一緒に寝たりしても良いのです。
赤ちゃんの性格やママの気持ちもそれぞれなので、これが絶対正解だよという寝かせ方はありません。
この記事の寝かせ方をいろいろ試していただき、今よりストレスなく寝かせられる方法に出会うお手伝いができたらうれしいです。







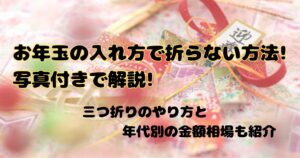


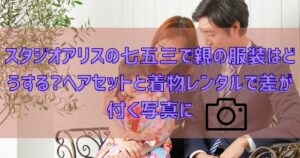
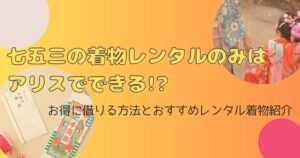
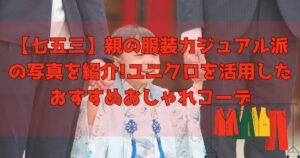
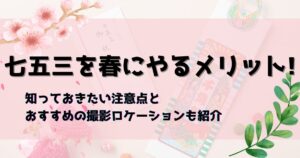
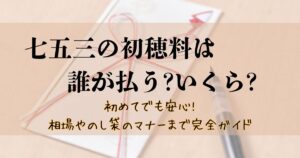
コメント